2017.07.31
ああやめてくれ!生ビールの“泡を切られる思い”とは?
伝説の酒エッセイスト、オキ・シローがこだわった生ビールの泡にまつわるお話
「泡で飲む生ビール」
白い泡があってこその生ビール。ぼくはそう思う。だから、ジョッキの三分の一近くが泡という生ビールが、いちばん好きだ。ジョッキが空になるまで、白い泡を割って飲みつづけたい。これがぼくの理想のスタイルだが、実際はなかなかそうはいかない。
普通のビールより長持ちする生ビールの泡でも、見ていると一秒に一ミリぐらいずつ消えていってしまう。大ジョッキなんかでのんびり飲んでいると、最初の二口、三口ぐらいで、もう泡がなくなっていたりする。これでは面白くないので、独りで生ビールを飲む時は、ぼくは小さいジョッキで頼む。これだと、きゅーっ、きゅーっとのどで勢いよく飲みさえすれば、なんとか泡が最後まで保ってくれる。
こんなにぼくにとっては大切な泡なのに、ビヤホールで見ていると、ジョッキからあふれ出た泡を、いとも無造作に木のへらで払い落としてしまう。ああ、もったいない、こんもりと盛り上がったままでいいのに。その度に、ぼくは無念に思えて仕方ない。あまりの無念さに、そんな時の気分のことを“泡を切られる思い”なんて、自分だけの言葉をつくったりしているぐらいだ。

あまり格好なんか気にしていると、特にジョッキに入って出てくる生ビールは、うまく飲めない。たとえ泡が鼻や、時にはおでこについたっていいじゃないか。はしたないと思うのだろうか、女の人がせっかく泡のある生ビールをチビッチビッと飲んでいるのを見ると、心底がっかりしてしまう。
二年ぐらい前だろうか、仕事の打ち合わせがすんだ後、若い女の編集者をビールに誘ったことがある。まだ若いお嬢さんで、特に目立つところのない、しかし見るからに品のいい人だった。口数も少なく、ぼくもしゃべることが不得手で、堅苦しい雰囲気がつづいていたため、夕方だったこともあって、ちょっと誘ったというわけだ。

「ああ、おいしい!」
グラスから口を離してそういった彼女の、ちんまりとした鼻の頭には白い泡がついていた。その思いがけない見事な飲みっぷりを見て、ぼくはいっぺんに彼女が好きになってしまった。四口ほどで飲み終えた彼女に、もう一杯どうかとすすめた時の、「はい、もう一杯だけいただきます」という返事も、実にきっぱりとしていてよかった。
それ以来、打ち合わせや原稿渡しの後で、彼女が帰社する必要のない時は、よく生ビールをつきあってもらった。そして、それはぼくの密かな楽しみでもあった。
ところが、半年ほど前のある日のこと。
「こうして生ビールをご一緒させていただくのも、今日限りになりました」
彼女の婚約者が転勤となり、やむを得ず退社するのだという。あの見事な飲みっぷりがもう見られないとは、なんとも残念無念。「それはおめでとう」と口では祝福しつつも、ぼくはまさに“泡を切られる思い”だった。
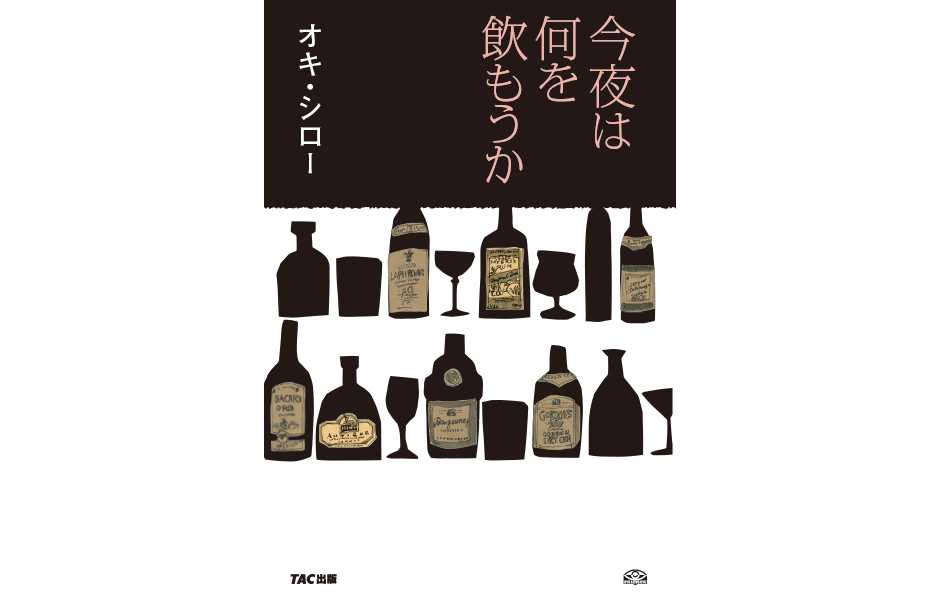
● オキ・シロー / コラムニスト
メンズ・マガジンのチーフエディターを経て、執筆活動に入る。主に酒をテーマにした掌編小説やエッセイなどを発表。著書に『ヘミングウェイの酒』(河出書房)、『寂しいマティーニ』(幻冬舎文庫)など。本文章は、『今夜は何を飲もうか』(TAC出版)より再掲。











