2022.01.24
スティーブ・ジョブズ、小野二郎、スティーヴン・ホーキング。時代を変えた男たちはどこが違うのか?
時代に爪痕を残すような男たちは普通の人間とどこが違うのでしょう? 映画ライターの牧口じゅんさんが偉人たちの伝記映画から彼らのサクセスした秘密に迫ります。その前編です。
- CREDIT :
文/牧口じゅん イラスト/ゴトウイサク
これまでどれだけの人が、「常識」や「いやいや、不可能だろ」という無責任な言葉によって、可能性を狭められてきたことか。そう考えると、世間が無責任に生み出す障壁を打ち破ることが、成功者になる大前提ということなのかもしれません。つまり「常識破り」であることが。
ある成功者から、「人と違うことをしないと成功者にはなれない」と言われたことがあります。つまり人と同じことをしていては、時代は切り開けない。では、時代に爪痕、足跡を残し、世界に変化をもたらす成功者は、多くの人といったい何が違うのか。その何かを映画の中に探しに行きましょう!
■ 映画 『スティーブ・ジョブズ』 (2016年)
冷徹なまでのミニマリスト 「スティーブ・ジョブズ」
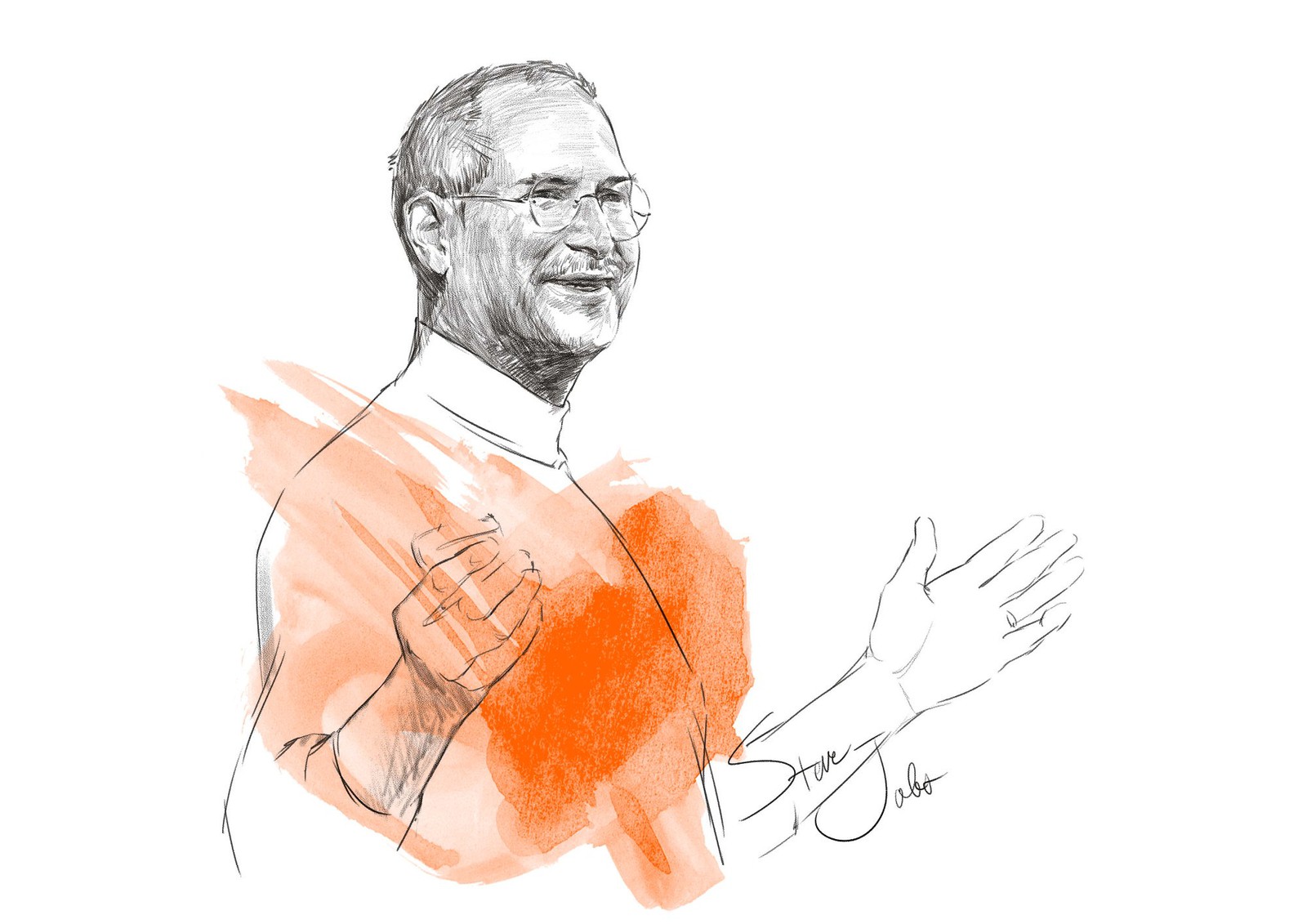
本作では、ジョブズ発案の革命的な家庭用PC3種、Macintosh(1984年)、NeXT社のcube(1988年)、iMac(1998年)の記者発表直前の彼を描いています。面白いのは、大仕事を前にした彼と、彼を取り巻く人々とのやりとりから、ジョブズの人生を映し出しているところ。マシンガン・トークの中に、アップル・コンピュータ創設のエピソード、その後の大成功と失速、家族やスタッフとの確執、ジョブズの哲学、心理などを、見事に盛り込んでいるのです。
物語は、1984年のMacintoshの発表会直前から始まります。「ハロー」と言うはずの新作PCが、それを言わないため、舞台裏ではジョブズがイライラしています。どうにもならないというスタッフの意見を無視し、どうにかしろと無理を言うのです。凡人ならば諦めそうなことも、必要だと信じれば強いこだわりを押し通すジョブズ。
一方で、他のソフトとの互換性など、不要だと思うことは潔く省いていきます。その一例が、盟友スティーブ・ウォズニアックとのやりとり。Macintosh発売まで、アップル社の稼ぎ頭だったAppleIIのチームに、会見で謝辞をとの提案を一蹴。過去の遺物に言及することは、新作発表会には相応しくないと何度も拒絶。iMac発売の際には、大勢のスタッフの面前で、ウォズを完膚なきまでにたたきのめすのです。ウォズを大切にしているにもかかわらず。
別のスタッフに、こう言われるシーンがあります。「どうして嫌われたがるのだ」と。するとジョブズはこう答えます。「嫌われたがっているわけではないが、嫌われても構わない」と。例え大事に思っている人の意見でも、違うと思ったことは徹底的に排除し、感情に決して流されない。その冷徹さが革新には必要なのでしょう。本作で際立つ「毅然と要・不要を見分ける精神」は、世界が愛するiPhoneやiPadのようなミニマルな商品デザイン、コンセプトに反映されています。常に同じ服を着続け、禅を愛した彼らしさに肉薄した人物描写が秀逸なのです。
実は、2013年にアシュトン・カッチャー主演で同じタイトルの映画が撮影されています。カッチャーがジョブズそっくりだと話題になりましたが、私は断然こちら、ダニー・ボイル版が好き。作品に漂うスピード感や緊張感が、その時どきのジョブズの精神性を映し出していると思うから。伝記映画において、外見が似ているかどうかはあくまでも表面的な演出の一部に過ぎないということを強く感じた作品でもありました。
■ 映画 『二郎は鮨の夢を見る』 (2013年)
徹底した仕事オタク 「小野二郎」
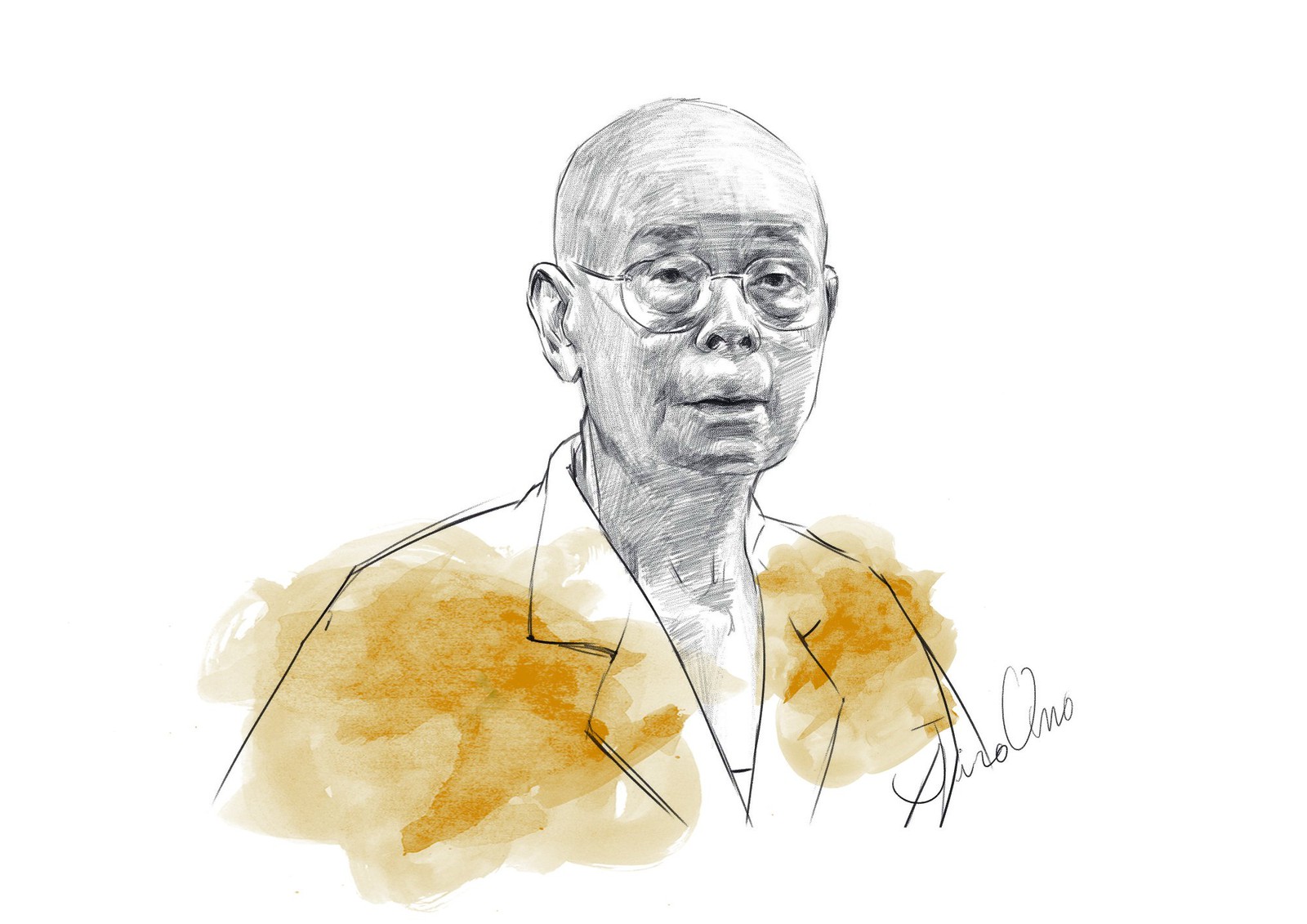
本作は、二郎氏が寿司にかける情熱、シンプルを極めたひとにぎりの美味が、どのように生まれ、どんな魅力を内包しているのかを、美しい映像と共に映し出しています。ミニマル・ミュージックの巨匠として知られるフィリップ・グラスの音楽が、ひたむきな職人魂と呼応。寿司が内包するストイックかつ芸術的な世界観を見事に表現しているのです。
自分への厳しさが、時に客を緊張させるほどの緊張感をももたらす二郎氏。彼をひとことで表わすなら「寿司に人生をかける真摯なオタク」とでも言いましょうか。もちろん、最上級の褒め言葉です。
地下にあるわずか10席の店舗で、化粧室も店外にある、そんな店がミシュランの三つ星を獲得するのは異例ですが、調査員が何度食べてもその味は「わざわざそのために旅行する価値のある卓越した料理」であることを否定しようがなかったといいます。理由として、他では味わえないオリジナリティがあること。そして、何度食べても同じ美味しさであること。ここに職人のマニアックさを感じずにはいられません。
これは哲学者としていかにもありそうなことだと内田氏。「ルーティンの中に身を置いていると、わずかな変化が際立つから」なのだとか。私は、二郎氏も同じなのではないかと思うのです。ひとつの技を覚えるのに10年。それを毎日繰り返し、同じようにできるまで身体で覚える。寿司は、さらにそこへ自然的な要素が加わってきます。素材だけでなく、気温、湿度など自分がコントロールできないわずかな変化をも捉え、常に最高を保つために、日々気の遠くなるような鍛錬を重ねる。公私の区別をつけたがる人にしてみれば「古い」のかもしれませんが、私を律し公にのめり込むことでしか、手にできない種類の成功もあるのです。
「自分がやろうと思ったことに没頭しなきゃダメです。自分の仕事に惚れなきゃダメ」。そう話す彼、そして生活から垣間見える姿は、究極のオタク。夢に見るほどの「美味しい寿司」への執念が、成功を導いたのでしょう。
いつも同じように美味しいと評されている二郎氏の寿司ですが、私が思う美味とは、次に食べた時に、自分の記憶のさらに上を行っているもの。美味しかった記憶を上回るには、きっと少しずつ進化していなければいけないはず。二郎さんのお寿司もきっとそうなのだろうと、未だに一度も「すきやばし二郎」に行く機会に恵まれていない私は、思いきり想像を膨らませながら本作を観ていたのでした。
■ 映画 『博士と彼女のセオリー』 (2015年)
難病すらユーモアで乗り越える、圧倒的な人間力 「スティーヴン・ホーキング」

とても印象的なのが、スティーヴンのユーモアセンス。自分の専門分野のみならず、クラシック音楽、文学など多くの引き出しを持っていることもあり、文系女子であるジェーンとの会話は、知性に溢れながらもとても軽妙。しかも、知識をひけらかすのではなく、常に面白い雑学も笑いを交えているのです。
なぜ、ブラックライトの下で、男性のシャツと白い蝶ネクタイが、女性のドレスよりも光っているのか、という話もロマンティックに語ります。「それは、Tideという洗剤に紫外線に反応する蛍光剤が入っているから。星が死ぬ時は紫外線を放射するんだ」と、パーティー会場で目の前に広がる風景を宇宙に見立てるスティーヴン。そしてデートの翌朝、彼女の家のドアの前に、Tideを置いておくのです。理系、しかも天才とくれば、暗くて堅物で奥手という先入観をもちがちですが、そのイメージを見事に打ち砕き、ジェーンを笑顔にし続けます。
笑いのセンスも素晴らしいですが、相手を頭ごなしに否定せず、反論も喜んで受け入れるという余裕も素晴らしい。ジェーンは敬虔なクリスチャンですが、科学者である彼は無神論者。それでも、彼女を教会の前で待っていたり、互いの意見をぶつけ合ったりする時も常に笑顔。その人間力には脱帽です。
糟糠の妻に三行半?と思う人もいるでしょうが、ジェーンが素直に応じたことからも、二人の中で、他人には理解できない「納得」があったのだと思います。ジェーンに「彼がそう言うなら仕方がない」と思わせる説得力も、彼にはあったのでしょう。それはすべて、彼がそれまでに見せてきた魅力=人間力によるものだと感じました。
その後、看護師エレインと再婚! エレインと出会った時の彼は、電動車椅子に乗り、自力では話せず、スペリングボードで意思疎通をしていました。アルファベットが記されたボードを使って、一文字ずつ言葉を綴るという途方もないコミュニケーション。その不便をものともせず、女性を魅了しているのです。どんな時もチャーミングで、ユーモアを絶やさない彼の人間力こそ、支援者を周囲に集め、偉業を成し遂げるための環境を作ったと言ってもいいでしょう。
余談ですが、スティーヴン本人のユーモアセンスに直接触れることのできる作品が。彼は科学者たちの日常を描いた米国のシット・コム『ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則』の常連でもありました。彼自身の役で登場し、かなりパンチの効いたブラック・ジョークを繰り出していました。同番組には、テスラのイーロン・マスクや、マクロソフトのビル・ゲイツ、アップル社創設者のひとりスティーブ・ウォズニアック、『スター・ウォーズ』のマーク・ハミルらそうそうたる成功者が自身役でカメオ出演しています。時代を象徴する大物成功者たちには、ユーモアのセンスと余裕もつきものなのだとつくづく感じました。
※後編に続く
● 牧口じゅん
通信社、映画祭事務局、映画サイト編集部勤務を経てフリーランスライターに。女性誌や男性誌を中心に、映画紹介、コラム、インタビュー記事を執筆。フードアナリスト、ドッグマッサージセラピストの資格を持ち、映画を絡めたライフスタイル系原稿も手掛ける。











