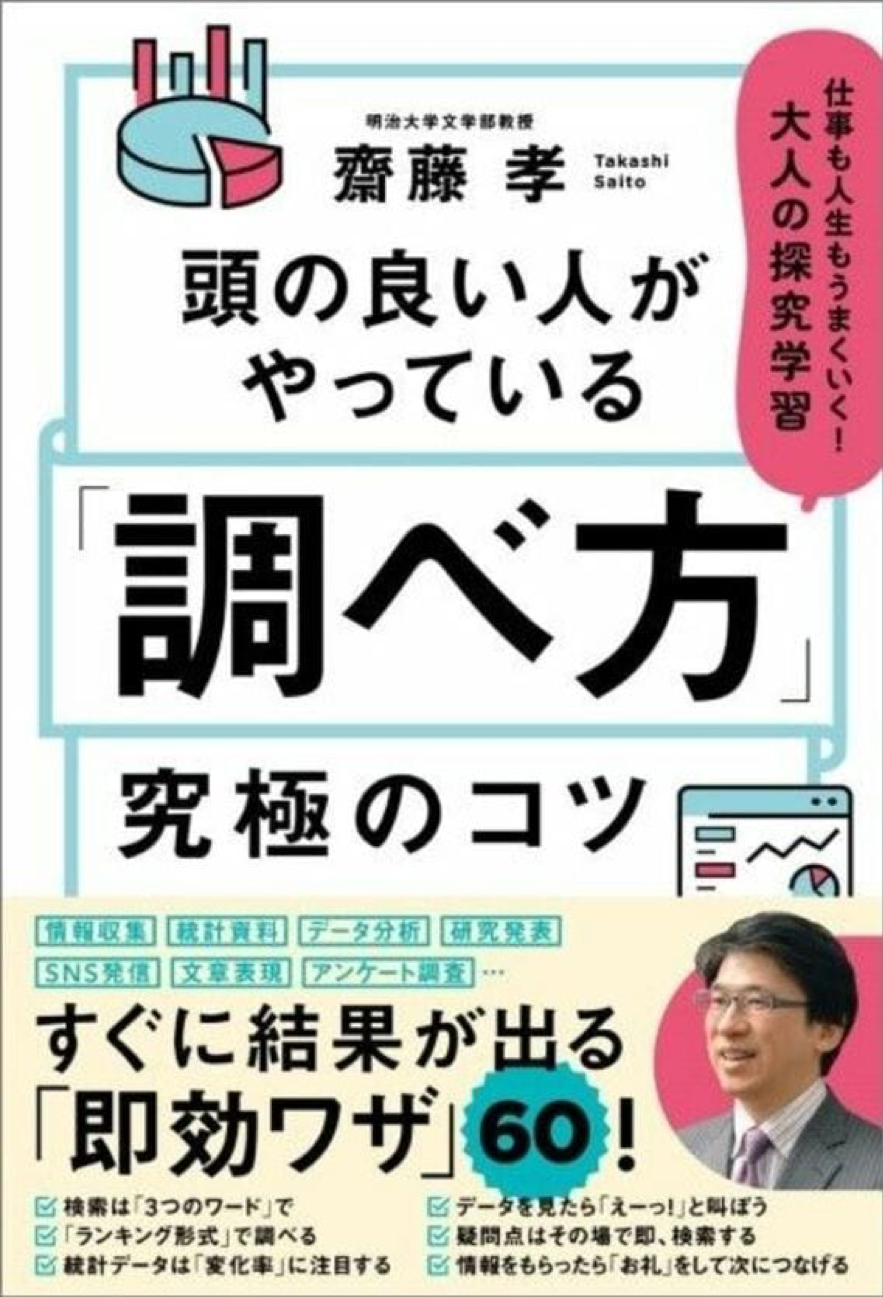2022.09.03
「事実と意見を混同する人」はトラブルメーカー!?
ネットニュースのコメント欄にも目立つ事実と意見の混在。事実とは本当にあったこと、意見とはその人が考えたことです。自分の意見を事実のように扱って根拠にする、トラブルメーカーになっていませんか?
- CREDIT :
文/齋藤 孝(明治大学教授)
齋藤 孝氏の新著『頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 仕事も人生もうまくいく! 大人の探究学習』から一部抜粋・再構成してお届けします。

疑問や違和感を持ったら、とりあえず調べてみる
2019年に、秋田魁新報という地方紙のスクープ記事が、優れた報道の担い手に贈られる新聞協会賞(2019年度)を受賞しました。
その記事の内容は、ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」の配備候補地選定をめぐって、防衛省の調査報告書に事実と異なるデータが記載されていることを独自調査によって明らかにしたというものです。
発端は、秋田県秋田市と山口県萩市・阿武町が同システムの配備候補地になったことでした。秋田魁新報社の記者は、「なぜ秋田市が候補地になったのか」「この候補地は住宅もある市街地に近い。危険ではないのか」と疑問に感じ、独自の調査を開始しました。
ほかの候補地を不適地とした理由の中に、周囲の山がレーダー波を遮るから、というものがありました。防衛省の報告書では、男鹿市にある本山の仰角を15度と記載していました。秋田で取材活動を続けているその記者は、その記載内容に違和感を抱き、実際よりも山の高さを誇張しているのではないか、との仮説を立てたのです。
三角関数で計算してみると、本山の仰角は4度という数字が導き出されました。4度と15度ではまったく異なります。
記者が現場に足を運び、スマホを使って太陽の角度がわかるサイトで調べたところ、やはり4度であることが示されました。そして後日、改めて専門業者の力を借りて測量をした結果、やはり仰角は4度であることが判明。これを受けて、防衛省の調査データにミスがあったと報じ、全国的な反響を呼んだのです。
本来、官公庁が発表するデータは信頼性が最も高いものであり、疑念を抱こうともしない人が大半でしょう。そんな中、「なぜ秋田市が候補地になるのか?」という疑問と、データへの違和感を出発点に、自分の力で調べた記者の行動力は称賛に値します。
日常で疑問や違和感を持ったら、曖昧にせず、実際に調べてみる姿勢が大切です。あきらめず調べていけば真実に到達できますし、調べる力も確実にアップします。
「願望」や「思い入れ」で仮説を立てることも大切
という疑問や違和感を持った際、あなたの頭の中で「違和感センサー」を働かせることは、「調べる力」を身に付けるためにとても大切です。
違和感センサーが何かを感知したときは、その都度、情報を詳しく調べる習慣を身に付けてください。そうした習慣を繰り返すうち、何かのグラフなどを目にしたときに「これは正しそうだ」「これは間違っている」などと直感的に理解できるようになります。
ただし、「調べる力」の原動力は違和感センサーだけではありません。「こうあってほしい」「こうなのではないか」といった願望や思い入れを持つことも重要です。願望や思い入れも「調べる力」の大きな原動力となるのです。思い入れが偏見につながっては元も子もありませんが、個人的な思い入れをもとに何かを調べ続けた結果、大きな発見につながるケースもあります。思い入れが生み出す力をあなどってはいけません。
京都大学で宇宙物理学を研究する嶺重慎教授が面白いことを語っています。近年の天文学の画期的な業績に、太陽系外惑星の発見があります。この業績により、スイス・ジュネーブ大学のミシェル・マイヨールらにノーベル物理学賞(2019年)が贈られました。
ほんの30年くらい前まで、天文学者たちは太陽系外の惑星など見つかりっこないと考えていました。しかし、マイヨールが「惑星が見つかったら面白いなあ」と妄想し、観測したところ、太陽系とはまったく異なる惑星の存在を発見しました。
度肝を抜かれたほかの研究者たちがそのあとを追って研究を行った結果、今では約5000個もの惑星が見つかっています。しかも、面白いことに、惑星の発見はマイヨールにとってメインの研究ではなく、サイドワークだったというのです。
嶺重教授は、これらのエピソードをもとに、研究者にとって重要なのは妄想する力であるといいます。科学の世界だけでなく、ビジネスの現場でも「こんなものがあったらいいな」という妄想を起点にして調べを進めていった結果、イノベーションの種が見つかることもあります。何事も「どうせ駄目」「調べる価値なし」などと決め付けてはいけません。
自分の間違いに気づいたら、すぐに調べて訂正する
一方で、思い込みの情報が間違いだとわかるケースも当然あります。
私は、かつて著書で『徒然草』について記述した際、著者を「吉田兼好」と表記したところ、出版社から間違いではないかと指摘された経験があります。
確かに「吉田兼好」と学んだ記憶があったので「そんなはずはない」と思い、自分で調べてみました。すると、近年の研究では吉田姓は後世になってから普及した通称であり、吉田とするのは間違いであるという説が主流になっていると知りました。現在の中学校の教科書には「兼好法師」と記述され、「吉田兼好」では若い人はピンとこないのです。
こうして、自分で調べて納得した私は、それ以降は「兼好法師」という表記を使うようになりました。
人は自分では気づかない思い込みをたくさん持っているものです。『秘密のケンミンSHOW 極』(読売テレビ・日本テレビ系)というテレビ番組があります。全国の出身県別にタレントが出演し、故郷のソウルフードやユニークな慣習、県民性などを紹介するバラエティ番組です。
この番組を見ていると、県境をまたぐだけで地域の文化が一変する様子がわかります。
先日、大学で学生に「安住アナウンサーっているよね」と話しかけたところ、1人の女子学生が「わからないです」と答えました。「なるほど。君はもしかして秋田県出身ではないですか?」と質問したところ、「どうしてわかったんですか?」と驚いていました。
秋田県にはTBS系のテレビ局がないので、全国的に知名度のある安住紳一郎アナも、秋田県民にとっては「知らない人」ということにもなるのです。このように、自分にとっての常識が、実は全国的に見れば非常識というのはよくあるパターンです。ですから、自分の思い込みが覆されても気にする必要などありません。「まったく違っていたな」と苦笑いしながら、正しい知識を調べて受け入れればよいのです。
「事実」と「意見」を分ける習慣を身に付けよう
ネットニュースのコメント欄などを見ていても、事実と意見が混在しているコメントや意見ばかりを主張している偏ったコメントが目立ちます。
事実と意見が混在すると、何を主張したいのかが不明瞭になります。また、自分の意見を事実のように扱って根拠にすると、相手から信用されないだけでなく、トラブルのもととなりかねません。
たとえば、個人的な意見を根拠として「今の若者はテレビを見ずにYouTubeだけ見ていると思うので、YouTubeに広告を出しましょう」などと主張するのは問題です。この場合には、若者によるテレビとYouTubeの視聴時間の差について調べてみるなど、きちんと事実を提示することが重要です。
ハンガリー出身の作家アゴタ・クリストフが書いた『悪童日記』(早川書房)という作品があります。この作品には、戦時下で食べ物もない大変な状況に置かれた双子の少年が、独学で読み書きを学び、さまざまな訓練をする姿が描かれています。
物語は、ノートに書いた「作文」という体裁で書き進められています。ノートには意見(主観)を排除し、事実だけを書かなければならないというルールがあります。そうして事実だけを書く訓練を通じて、少年たちはリアリストに成長していくのです。
事実と意見の区別によって人間はどう変わるかを考える上で、非常に示唆に富んだ物語だと思います。
事実と意見を区別する習慣が身に付くと、ビジネスの場で会議を円滑に進行する能力なども備わります。「ここまでは事実ですね。では、ここからご意見をどうぞ」などと整理しながら発言を促すことで、仕事が円滑に回るようになることでしょう。
また、意見が対立したとき、「この事実だけは共有できますか?」などと事実を共有することを通じて、お互いの認識を近付けていけるようにもなります。
『頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 仕事も人生もうまくいく! 大人の探究学習』
調べて⇒伝えて⇒結果を出す! 齋藤式・秘伝の「調べ方」テクニック満載
●情報収集・統計資料・データ分析・研究発表・SNS発信・文章表現・アンケート調査……、すぐに結果が出る「即効ワザ」60連発!
●司馬遼太郎、吉村昭、立花隆、野村克也、南方熊楠、小林一三、早川徳次、大橋鎮子、レイチェル・カーソン、フローレンス・ナイティンゲール……、データを活用して偉大な業績を残した達人たちの「調べ方」を徹底レポート!
●「統計データの読み方・作り方コーナー」も充実! 小学校・中学校・高校の「探究学習」に活用できる実践的なテクニックを、齋藤孝先生が実践コーチします。
齋藤 孝・著 学研プラス 1540円(税込)
※書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします