2023.03.31
【vol.15】「いけばな」を識る(2)
「いけばな」はたった1本の花で空間を変えることができるアートだった
いい大人になってお付き合いの幅も広がると、意外と和の素養が試される機会が多くなるものです。小誌・石井編集長(49歳)が、最高峰の和文化体験を提供する「和塾」田中康嗣代表のもと、和のたしなみを学びモテる旦那を目指す連載。今回のテーマは「いけばな」、その後編です。
- CREDIT :
文/牛丸由紀子 写真/田中駿伍(maettico) 撮影協力/草月会 取材協力/ダイナースクラブ(運営会社:三井住友トラストクラブ)

第15回のテーマは「いけばな」。前編ではいけばなの歴史や日本の自然信仰や美意識から、いけばなが発展し、華道家はアートディレクター的役割のひとつだったと知り、「いけばなはアートだ!」と感激の石井編集長。後編では先生のデモンストレーションを参考に、石井編集長が実際にいけばなに挑戦します。導いてくださるのは、草月流の本部講師であり国内外でいけばな作家としてもご活躍の大泉麗仁(おおいずみれいと)先生です。さて、石井編集長のいけばな体験、どんな作品ができあがるでしょうか?
朽ちる美しさを知る日本、西洋との美意識の違い
石井 いや、かなりやる気になっています(笑)。初歩的な質問なんですが、西洋にもフラワーアレンジメントがありますが、日本のいけばなの違いってどんなところにあるんでしょうか?

田中 桜が散った後も美しいと言うのが日本人。朽ちた花を美しいとは、西洋の美意識ではあまり言わないんじゃないかな。受け手に考える余地を与えて、捉え方を委ねているところもありますよね。水墨画も描いていないところを想像させるような描き方ですから。
大泉 西洋は足し算の美学、日本は引き算の美学と言われるのもそういう部分だと思います。
田中 舞台も、西洋演劇は情景説明ができる書割や美術になりますが、日本の能などは、小道具もほとんどなく、背景は松の絵だけですからね。
【ポイント】
■永続を望む石の文化と、移ろいに美を感じる木の文化
■美しさを感じるのはシンメトリー(西洋)/とアシンメトリー(日本)
■西洋は足し算の美学、日本は引き算の美学

空間を埋めるのではなく“間”を作る
石井 それを聞いてちょっと気持ちが楽になりました。自分がやればそれは自分の花になる、ありのままでいいんだと言ってもらった気がします。
大泉 そうですね。ぜひ、そんな新たな美しさをみつけていただきたいと思います。最初に私がいけながら、いけ方の考え方を説明していきますね。まず花をいける時には、どこに置くのかということ。玄関なのか、広間なのか、あるいはもっと大きなパーティー会場なのか。その場所によって表現も変わりますし、お花はおもてなしのひとつですから、意味合いも変わってきます。
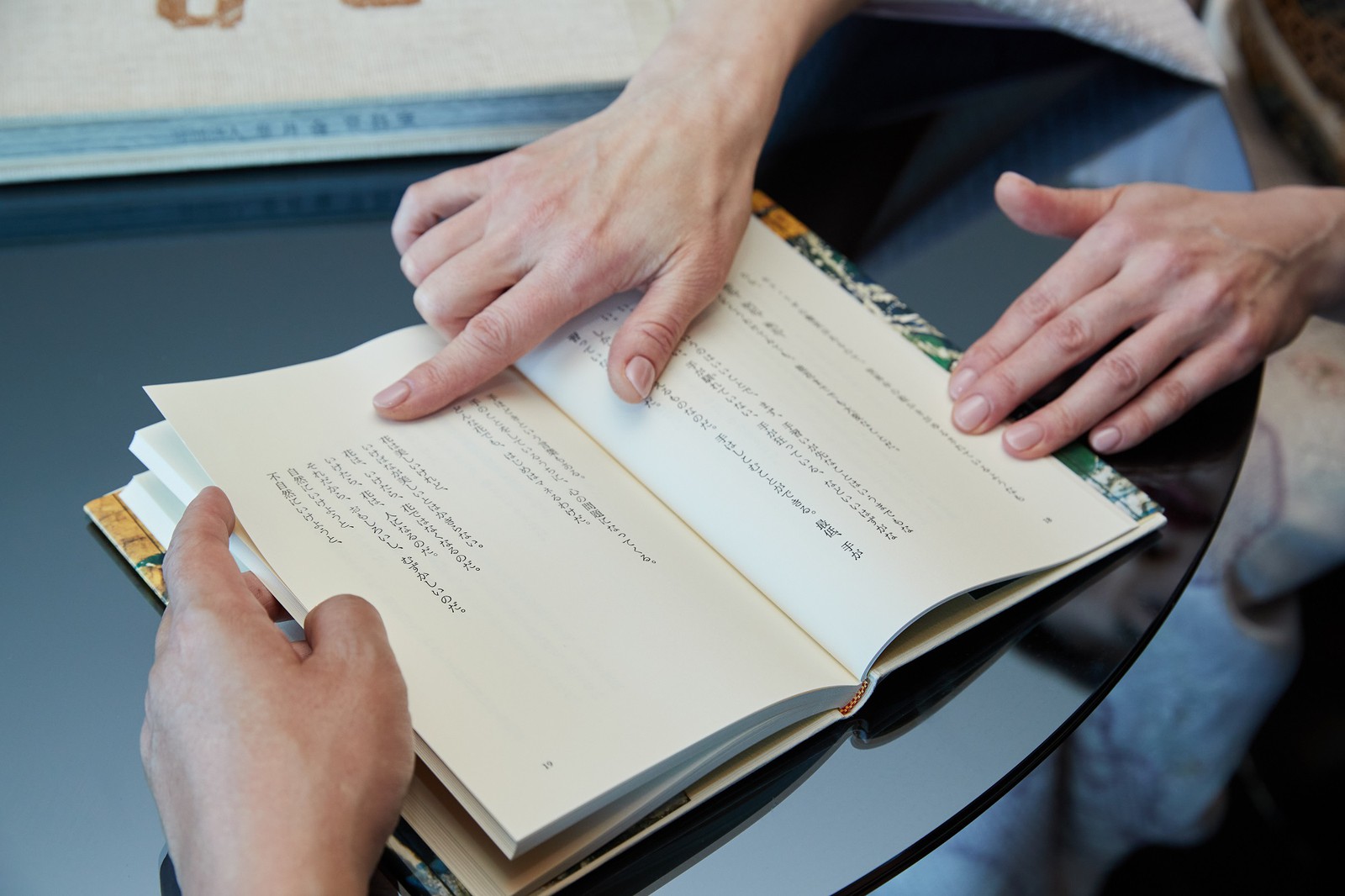
大泉 いけばなの場合は、まず空間があって、そこにどう構成していくか、どこに“間”を作るのかを考えていきます。
田中 “間”を作るというのは、実に日本らしい。フラワーアレンジメントは、間を埋め尽くしていくもので、いけばなは花のないところがむしろ大事だったりしますから。
【ポイント】
■永続を望む石の文化と、移ろいに美を感じる木の文化
■フラワーアレンジメントは間を埋め尽くす/いけばなは間を作る
■いける前に、まず置く場所を想定する
重要なのは「線・色・塊」の3要素

いける枝や茎を切る時は、「水切り」と言ってボウルに入れた水の中で切ると、水揚げが良くなり長持ちします。

大泉 そうですね、もう瞬間的に感覚でやっています。また必要に応じて、枝や茎に指で少し力を加えて曲げるようにして“ためる”という技術を使って、動きをつけたり、振りの向きを変えたりします。特に背の高い器の時は、このためる技術をよく使っていけていきます。
石井 ためると、枝と枝を重ねるだけでもうまく留まるものなんですね。
田中 でも枝をどこからどう入れていくのか、空間をどう使うのか、すごく頭を悩ませますよね。大きな作品だと奥行きもありますから。

石井 いけていく中で、ポイントにすべきことはありますか?

田中 なんとなくいけるのではなく、その要素を考えながら形を整えていくのが重要というわけです。
大泉 それと見せたいと思うところを引き出していくこと。それ以外に余分なところは、マイナスしていく。引き算をしていくと、流れがきれいに見えてくると思います。

大泉 その素材を見てからになります。やはり枝ぶりも同じものが手には入らないですので。色味も例えば今日の素材だと、白と黄色だけでもいいんですが、少し華やかなイメージにしたいので、青いデルフィニウムと赤いダリア、クワズイモの葉を使って色を足していきます。
田中 これで完成ですね。見る位置によって、印象がすごく違いますね。おもしろいな。

田中 少ない数で表現しなくちゃいけないから、これは花をたくさん使うより難しそうだな。
石井 どこの花を残すのか、ちょっと切るのに勇気がいりますよね(笑)。う~ん、そこを残すのか⁉


石井 いや、もう、とことん削って、本当に引き算の美ですね。でも、つぼみをひとつ残しているところがまた素晴らしい。

【ポイント】
■切る時は枝や茎を水の中でカット。水揚げが良くなり植物が長持ちする
■枝や茎に指で少し力を加えて曲げる“ためる”技術を活用
■枝によっては流れる方向があるので、その流れを活かしていける
■いける時は、いけばな3要素「線・色(しき)・塊(かい)」に注目
選んだのは難関花材&花器!? 石井編集長が挑戦!
大泉 花材と花器、どちらから選んでも良いのですが、まず花を見てから、それに合う花器を選んだ方がやりやすいと思います。

田中 そうすると「ぼけ」の大きな枝をいれられる少し大きめの花器が必要ですね。

大泉 この場合、枝や茎は底につけずに、器の内壁に沿っていけるといいと思います。切り口は内壁に沿うように斜めに切ってください。
石井 う~ん、なかなかバランスが難しいですね。

田中 迷ったらどんどんいけて、後から切って落としていってもいいんですよ。
石井 うわ~、枝のどこをきるのか、どの方向にさしていくのか、ホント悩むな~。

田中 花器の中が見える分、枝の方向や水の量など考える要素も多くなる。初心者にはちょっと難しい花器だったかも?
石井 いやほんと、がんばります(笑)。でもなかなかうまく留まらないな。

石井 なるほど! そういう工夫も必要ですね。でも、バランス考えてカットしたり、むちゃくちゃ難しいです。

石井 なります、なります。すごくおもしろいですね。やってよかったな。あとは葉ものを入れて、完成です。先生、どうでしょうか!
大泉 初心者とは思えない作品! 最初に大きな「ぼけ」を選んだ時は、難しいかなと思いましたが、暴れている枝ぶりの良さを上手に活かすことができ、空間がガラッと変わりましたよね。また、色をとても意識されていたこともよかったです。まとまりもありますし、白を入れたことで他の花がより引き立ったと思います。
田中 いや本当に大胆な作品ですよね。格付けチェックに出しても、気がつかれないんじゃないですか(笑)。
石井 いやいや、まだまだです(笑)。先生、いけばなのセンスというものは、僕みたいに今から始めても磨けるものなんでしょうか?

私自身、いけばながおもしろいと思ったのは、たった1本の花でも空間を変えることができると感じたからです。まずは1本でも少ない素材でも、難しく考えずいけてみてほしいですね。
石井 いけばなは、まさに空間に立体を描くアート。歴史からいけばな体験を通して、それがよくわかりました。実際にかなりハマりました(笑)。花は女性に渡すためだけではなく、これからは自分のためにも買って、いけてみたいと思います。今日はありがとうございました!

【ポイント】
■花材と花器、どちらから選んでも可
■透明なガラスの花器は、花器の中の枝の見え方や水量にも注意
■たった1本の花で空間は変わる
■基本の型や技術を学んだ先に、いけばなの個性が現れる

● 大泉麗仁(おおいずみ・れいと)
いけばな草月流本部講師として指導にあたるほか、自由が丘と代官山でいけばな教室、麗―rei―を主宰。2000年に草月流に入門し、竹中麗湖氏に師事。公共空間、店舗、イベント等さまざまな空間におもてなしの花を提案し、いけばな作家としても活躍中。2004年 第86回草月展「新人賞受賞」、2009、2012年「新作能 オンディーヌ」能舞台にて苫屋制作や2015年パリ・日本文化会館にて能の舞台美術を制作。2012年「マルセル・プルーストへのオマージュ 失われた時を求めて」舞台公演にて、音と香りを融合させたいけばなパフォーマンスで、独自の世界を切り開いている。また、現代空間の中に人の心や呼吸に深く共鳴していくいけばなを目指しワークショップを開催。2022年には麻布十番ギャラリーにて個展を開くなど精力的に活動している。
HP/http://reito-oizumi.com/
Instagram/@reitooizumi
■いけばな草月流
1927年自由な創造と個性を尊重するいけばなを求めて勅使河原蒼風が創流。草月のいけばなは型にとらわれることなく、いつでも、どこでも、だれにでも、そして、どのような素材を使ってもいけることができ、いけ手の自由な思いを花に託して、自分らしく、のびやかに花をいけるのが特徴。また、時代とともに変化してきた草月のいけばなは、それぞれのご家庭で楽しむことはもちろん、ウインドーディスプレーや舞台美術など、社会のあらゆる空間に植物表現の美と安らぎをもたらしている。現在は、第四代家元・勅使河原茜のもと、子どもたちへの指導や「いけばなライブ」などの取り組みとともに、新しいいけばなの魅力を発信する流派として世界中で親しまれている。
HP/https://www.sogetsu.or.jp/

● 田中康嗣(たなか・こうじ)
「和塾」代表理事。大手広告代理店のコピーライターとして、数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め、2004年にNPO法人「和塾」を設立。日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行う。
■ 和塾
豊穣で洗練された日本文化の中から、選りすぐりの最高峰の和文化体験を提供するのが和塾です。人間国宝など最高峰の講師陣を迎えた多様なお稽古を開催、また京都での国宝見学や四国での歌舞伎観劇などの塾生ツアー等、様々な催事を会員限定で実施しています。和塾でのブランド体験は、いかなるジャンルであれ、その位置づけは、常に「正統・本流・本格・本物」であり、そのレベルは、「高級で特別で一流」の存在。常に貴重で他に類のない得難い体験を提供します。
HP/http://www.wajuku.jp/
和塾が取り組む支援事業はこちら
HP/https://www.wajuku.jp/日本の芸術文化を支える社会貢献活動

<ダイナースクラブ トラベルサービス・優待>
「ダイナースクラブカード」なら、国内の厳選された120以上のホテル・旅館で、優待や特典が受けられます。部屋のアップグレードや、ホテルでは朝食付き、旅館では食事のアップグレードといったうれしい特典をご用意。また、航空券や宿泊の手配・相談を旅行のエキスパートが受け付けるトラベルデスク、国内/海外約1300カ所の空港ラウンジを、ダイナースクラブ会員ご本人様は無料でご利用いただけます。
トラベルサービスのページはこちら
https://www.diners.co.jp/ja/travel.html
● 【ご招待制】ダイナースクラブ プレミアムカードの詳細はこちら
https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html
● ダイナースクラブの詳細はこちら
https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html











