2021.07.20
振り返らない男、加藤和彦/挑戦し続けた男たちの伝説【01】
その名が今も語り継がれているのは、きらびやかな活躍の裏側に、挑戦を続けるたゆまざる信念があったから。芸能界に伝説を遺した偉人の生き様を振り返ることで、希代のチャレンジスピリットが見えてきます。
- CREDIT :
文/山下英介 イラスト/Isaku Goto
天才はメンドくさい!
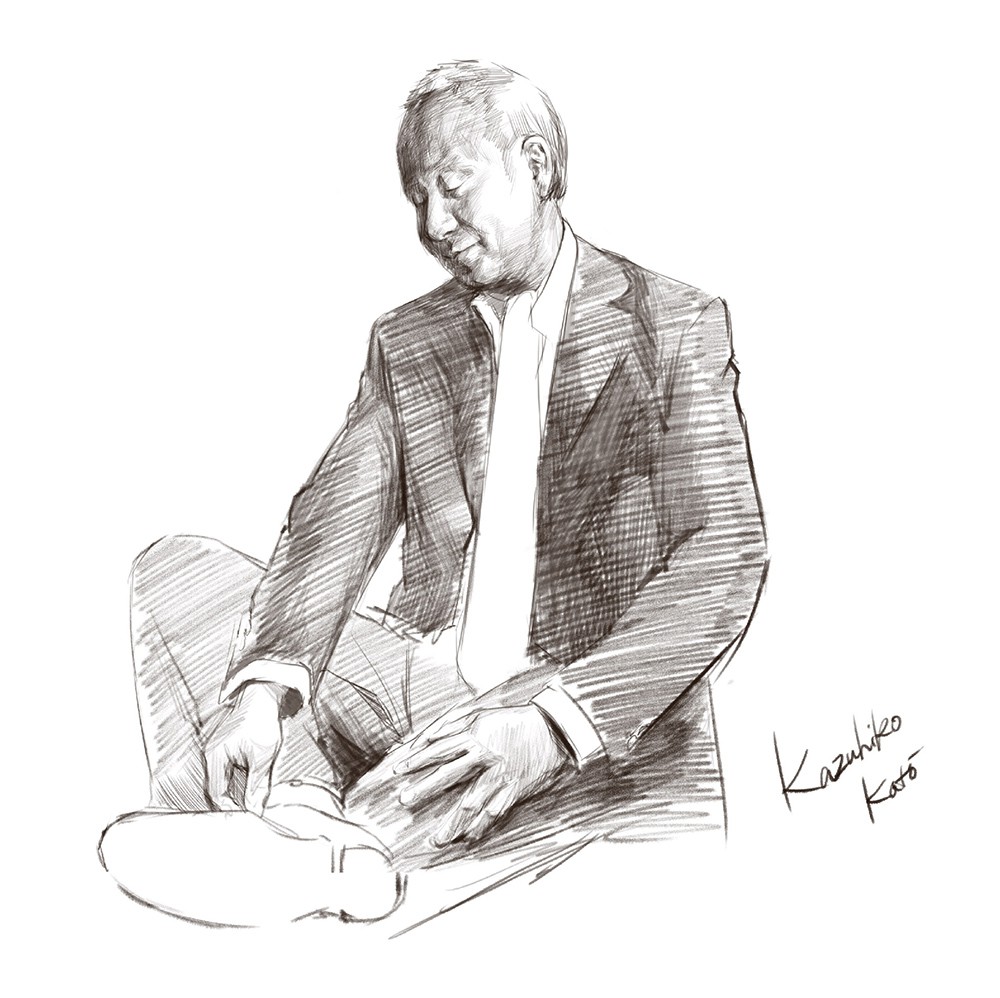
2009年に62歳で亡くなったミュージシャンの加藤和彦も、きっとそんな“メンドくさい”存在だったに違いない。なんたって、音楽においてもライフスタイルにおいても、彼ほどの速度で駆け抜けた人を、筆者は知らない。ここでは彼の音楽史に加え、それとは切っても切り離せないライフスタイル史を、同時に振り返ってみよう。
1960年代、アイビーからヒッピーへ
それが『帰って来たヨッパライ』の大ヒットと共にプロとして活動を始めた1967年頃になると、すでにアイビーを卒業。ヨーロッパ志向のJUNやMr.VANを着用し始め、髪型もマッシュルームカットに変わっていた。しかし「フォークル」解散後の1969年に初のアメリカ旅行を経験した彼は、早くもボブ・ディランに影響されヒッピーファッションで帰国。時代の空気と言ってしまえばそれまでだが、ファッションも音楽の嗜好も、1年単位で脱皮してしまう男なのだ。
1970年代、ロンドンから西海岸へ
同年から年に4、5回の渡英を繰り返し、現地のグラムロックとファッションに耽溺する。四畳半フォークの全盛期だった1971年には、高橋幸宏らと「サディスティック・ミカ・バンド」を結成。オレンジ色の髪にサテン生地のスーツ、ヒール高10㎝のロンドンブーツという、デヴィッド・ボウイ顔負けのスタイルでロールス・ロイスを乗り回し、周囲の度肝を抜いていたという。
同時期には「フォークル」のヒットで手にした印税をぶち込んで、当時の日本にはなかったPA(音の拡声機材のオペレーションシステム)会社を設立。加藤和彦が20代前半で作ったこの会社は、「日本の音楽シーンを10年進めた」と言われるほど、ポップ・ミュージック史において重要な役割を果たしている。
「ミカバンド」は「ロキシー・ミュージック」の全英ツアーの前座を務めるなど、本場イギリスでも強烈なインパクトを残すが、ボーカルであり妻でもあった、福井ミカとの離婚に伴って、1975年に解散。すると加藤和彦は、即座に英国趣味の家具をすべて処分。当時住んでいた川口アパートメント(東京都文京区に現存するヴィンテージマンション)の一室を、コロニアル趣味にリフォームしてしまった。
その頃取材で自宅に伺ったという知人ライターの証言によると、「部屋のど真ん中をガジュマルの木がぶち抜いていた」とのこと。彼女の記憶が確かなら、加藤和彦おそるべし。さらにその後はアメリカ西海岸ファッションに目を向け、1976年に創刊した『POPEYE』に度々登場するなど、西海岸流のスポーティなライフスタイルを若者たちに啓蒙する。当時のお気に入りは、アディダスの3本線が入ったスウェットやスニーカー……ってもう、早すぎてついていけないよ!
1980年代、空前絶後の貴族趣味
1980年代初頭の日本ではまだ珍しかった、ジョルジオ・アルマーニやジャンニ・ベルサーチのスーツを、ルイ・ヴィトンのワードローブトランク(それも2台!)に収納し、ポーターに運ばせ、ヨーロッパやカリブ諸島の5つ星ホテルを渡り歩くそのライフスタイルは、まるでゴールデン・エイジのハイソサエティ。
その本物にこだわる姿勢は徹底的なもので、レコーディングの際は自らコック服に着替え、プロ用の厨房を使い、30人を超えるスタッフに本格フレンチやイタリアンを振舞っていたという。ちなみにこの夫婦が六本木に建てた録音スタジオ付きの自宅は、地下にオートテニスコートを備えたロマネスク調の洋館。ファッション業界人の間ではちょっとした語り草になっていた。

京都の一般家庭で生まれた加藤和彦は、幾度もの脱皮を繰り返すことで、30代前半にして欧米のアーティストや上流階級にも負けない、本物のセンスと教養を身に付けたのだった。1980年代において「加藤和彦」という存在は、1920年代のF・スコット・フィッツジェラルドや1960年代のトルーマン・カポーティと同じように、スノッブのアイコンとして機能していたのである。
日本のサブカルチャー史における巨人と謳われた編集者の故・川勝正幸は、そんな加藤和彦のスタイルを“音活(音楽と生活)一致の美学”と評したが、だとするとスウェットばきで安いインスタントコーヒーを飲みながらこの原稿を書き殴っている筆者なんて、完全にライター失格。ドレッシングガウン姿の加藤和彦に「キミが僕の原稿を書くなんて100年早いよ」と怒られることは間違いない。ここからはビスポークスーツに着替えて原稿を書きます!
1990~2000年代、英国ビスポークからトム・ブラウンへ
もちろん音楽に関しても、市川猿之助(現・猿翁)とタッグを組んだスーパー歌舞伎を筆頭に、多彩な分野における先駆者であり続けた。二番煎じを禁じ手とする彼は、「フォークル」だろうと「ミカバンド」だろうと、絶対に“再結成”はせず、期間限定の“新結成”として、新しいアレンジ、メンバーで挑むことを自身に課した。つまり、加藤和彦は最後まで前向きで、格好良かったのである。だからこそ、2009年の“結末”には、誰もが驚いたのだった。
挑戦することと、孤独と向き合うこと
筆者を含めたファンは、エレガントに微笑んでいる加藤和彦の姿しか知らない。しかし“つくられた時代そのものの音を鳴らす”と言われたギターのテクニックは、どうやって身に付けたのだろう? 海外のミュージシャンと堂々と渡り合えた、見事な語学力は? ヨーロッパの貴族たちをも唸らせた、教養や社交の能力は? ……想像すればするほど、彼が一見華麗にしか見えない人生の裏舞台で密かに続けていたであろう凄絶な努力に、頭を垂れざるを得ない。
挑戦し続けるということは、孤独と向き合うことと同義である。そしてその孤独こそが、加藤和彦のいう“人生の副産物”として、彼の音楽にワインのような深みと優しさを与えてくれたことは、紛れもない事実だ。しかし、その“結末”を受け容れることは絶対にできない。ときには後ろを振り返ってもいい。ボロボロになってもいい。それでも走り続ける彼の姿を、ファンはずっと見続けていたかったのだから。











