2019.10.29
『ホモ・デウス』、書籍タイトルからどこまで想像して読むか
"超情報社会"と称される現代において、これからの私たちの暮らしはどうなっていくのか? そんなぼんやりとした疑問に新たな視点を与えてくれる名著を、読書の秋にリコメンドいたします。
- CREDIT :
文/岸澤美希(LEON.JP)
日進月歩でテクノロジーが進歩し続ける現代、「ふぁいぶじー」「あいおーてぃー」「あいおーしー」など新たなカタカナ単語が身の回りに登場しまくっていますね。なんだかハイテクになっていることは分かるけれど、気になるのは<わたしたち人間はドコに行くのか>。
そんな疑問に新たな視点から答えてくれる書籍を、秋の夜長のお供にオススメいたしますー。
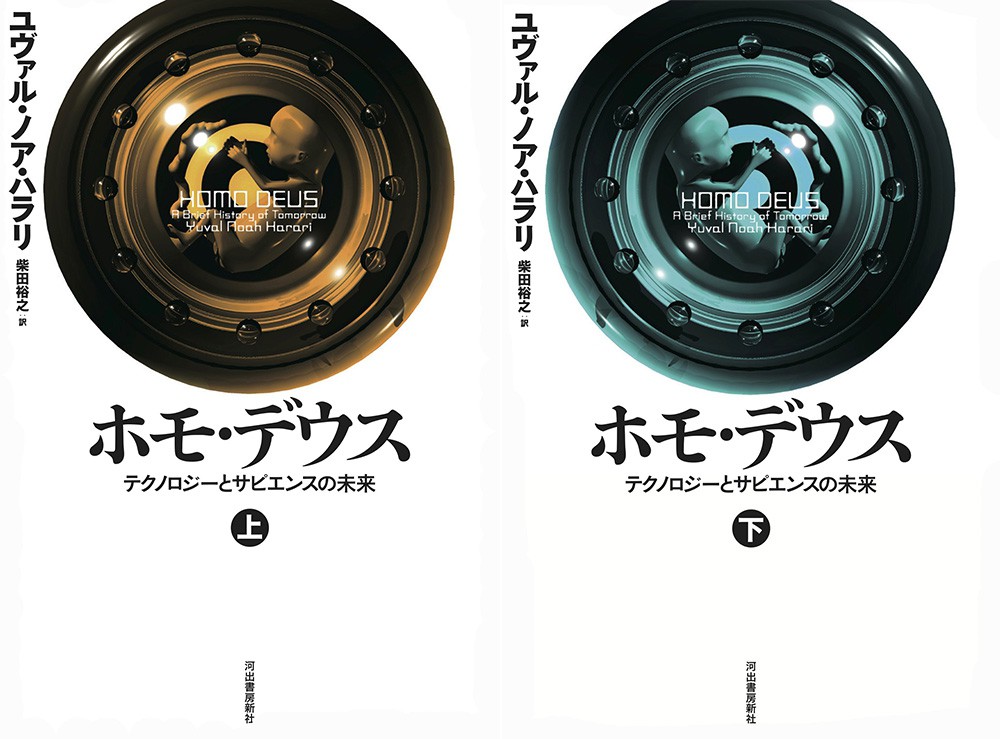
本著末の訳者あとがきにある「著者は他の人類種と区別するために、ホモ・サピエンスを「サピエンス」と呼ぶ」を加味すると、タイトルの意図は明快で、ホモ・デウス=デウス(ゼウス:全能の神)という新人類。
著者は、自らを"賢い人間"と名乗るホモ・サピエンスが神へとアップグレードするとき、想像を絶する格差が待っている言います。−−それでは、能わざるものは何故に存在するのか?
閑話休題。李登輝(り・とうき)元台湾総統が、来日中にとある湯呑に目に止めたというエピソードがあります。
そこにあったのは、以下の五訓。
「日常の五心」
一、「はい」という素直な心
一、「すみません」という反省の心
一、「おかげさま」という謙虚な心
一、「私がします」という奉仕の心
一、「ありがとう」という感謝の心
このような日本の精神性を形作った儒教には、
不為也、非不能也−為さざるなり、能わざるにあらざるなり−できないということは、大抵の場合できないのではなく、やらないということだ−(孟子)
という言葉があります。古の東洋思想の中には、"人間自身の行ないを問う考え方"があったということ。
さて、ここで抱ける疑問は、<我らに必要なことは、サピエンスがデウスになることなのだろうか>。
デウスを内包しているサピエンスは、いかにデウス足り得る資格を得るのか……。
−−と、ちょっと真面目なお話でしたが、超情報社会の行く末が気になる方は、ぜひご一読を。これで、するっとまるっとお見通しだー(笑) それでは、また次回のブログにて!











