当時はイートインを休業している店も多かったが、その空いた時間で今後の飲食業界の推移とどうしたら持続できるかを考え抜いた飲食店と、様子見を決め込んだ店とで大きな差がその後ついたと私は思う。

まだライバルがほとんどいなかったことが功を奏し、テレビに取り上げられたり、SNSで拡散された。なかでも右京グループは客の意見を取り入れて「大人のお子様ランチ」やご飯なしの酒肴セットなど人に寄り添うセットを開発。その過程で獲得した新規客が100個以上の弁当を頼んでくれるようになったという。ネットの時代は躊躇するより、まずは行動。意見を聞きながら修正するという過程が一番大切だということがよくわかる。

料亭で出される日本料理は作られてから食べるまで、時間が経つことを想定されているものが多い。カウンター割烹が全盛の今、そういう料理はともすれば古い形式と思われてしまうが、テイクアウトなら時間が経っても美味しい料理を提供できる技術を最大限に活かせる。接待がなくなったが故の苦肉の策だったのかもしれないが、料亭が直接、普通の客に向き合う決断をするのはかなりの決心だったと思う。
進化する一流店のお取り寄せ
◆治作の水炊き

◆「ラッセ」の「チーズラビオリ」
<今年1月初旬、コロナが武漢で感染してる記事をネットで読んだ瞬間すぐにマスクをラッセスタッフ全員分4ヶ月分を買った。パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)も買った。その時は、まだ日本のメディアはどこもコロナの事を放送していないんじゃないかな? 多分。>
10年前のラッセ創業当時から、飲食店でありながらフォーマットを作る側にシフトチェンジしようと決めていた村山さんにとって、コロナはある意味、背中を押す好機だったのだろう。

◆「にょろ助」の「うなぎ蒲焼」
この1年間、中華おばんざい、中華朝食開始など、コロナのフェーズに合わせたニュースを仕掛けていったが、現在ブレイク中なのは「にょろ助」といううなぎ店を中心に全国に拡大中の「うな重2尾入りで3900円!」というプロモーション。

保健所やデジタル技術など、これまで遠かった分野の研究も行い、時にはSNSでぼやきながら日々前進していったところが、美味しいお取り寄せやテイクアウト、デリバリーを生み出した。
今後は料理だけを考えているだけでは料理人は生き残れない——ずっと前からみんな気づいていながら行動に移せなかったことをコロナが動かしたんだと思う。その一方、客のほうはテイクアウト、デリバリー、お取り寄せなど多彩な選択肢を経験したからこそ、シェフが目の前で料理を作ってくれ、それを食べながら美味しい酒を飲み、会話を楽しむ外食の良さも再発見できた。まさに多様な食の楽しみを体験でき、楽しみの幅が広がった1年だったともいえる。
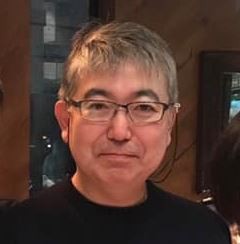
柏原光太郎(かしわばら・こうたろう)
1963年東京生まれ。(株)文藝春秋で食のEC「文春マルシェ」を担当。十数年前から食の魅力にはまり、食べるだけでなく、作る楽しみを普及させようと男性が積極的に料理をするコミュニティとして、2018年に「日本ガストロノミー協会」を立ち上げる。
LEON.JPでは以前、最愛の娘に向けて作り続けた弁当について執筆。
「パパから中学生の娘へ――332個めの弁当を作り終えた朝に綴る、父と娘の毎日弁当」
「旅立つ娘のために元祖弁当男子のパパが作った最後の弁当、その中身は?」
インスタグラム@kashiwabara_kotaro











