世界のアートマーケットで伸びるのは強いシンボリックなイメージを量産できる作家
三潴 日本には現代アートだけを蒐集して展示する国立現代美術館がありません。これは致命的に恥ずかしい話です。お隣の韓国にだって国立現代美術館が幾つかありますよ。それと現代アートのマーケットが小さいのです。その規模を数字であらわすと全世界のアートマーケットの3%ぐらい、せいぜい3000億円ほどだと言われています。マーケットが形成されていない文化では作家は育てられません。だから日本の作家が認められるには海外、特に欧米で成功することが大事になってきます。
欧米のマーケットでは、まずその作家に一つの特異なイメージとコンセプトがあるかどうかが重要となります。例えば村上隆ならスーパーフラットのコンセプトですね。奈良美智では、あの目のつり上がった少女のようなキャラクター化されたものです。そういう独自のシンボリックな特徴を持っていることが第一の必須要素で、なおかつ西洋の美術史に絡んだコンセプトがあることです。
そして二つ目の条件は、作品を大量に生産できる仕組みをもっていることですね。今世界で成功している作家はみんなそういう仕組みで作品を作っています。ジェフ・クーンズも村上隆も、みんな工房で作品を制作している作家ですから。現代のポップアーティストは、作品を必ずしも自分の手で作らず、むしろコンセプトを考えて、それを弟子たちが描いて、最後にサインするというのがスタンダードなんです。
かつてルネサンス期に、有名な作家たちはみんな工房を抱えていて、貴族や大商人たちから仕事を請け負いながら、独自の絵具や筆を独占したりしてお互いに切磋琢磨して技を高めあった。これと同様に、現代はシステム的に量産できる作家がマーケットでの取り扱いが伸びていきます。大量に作ることができて、しかも特徴があって、見たらすぐに誰の作品か分かるようなイメージがあると、世界では売りやすいんですね。こうして現在の世界のアートマーケットは拡張し、巨大化しています。
三潴 大量生産が前提となる背景には、供給が需要を喚起するマーケットになってきているという側面もあります。世の中にどんどん作品が供給されれば、それに応じて買う層が生まれるという流れができ上がっている。それは具体的にはアラブの王族やIT長者だったりするのですが、最近は文化的なアプローチができて、パトロンになるようなセンスのいい知的な富裕層も出てきています。ゆたかな文化の香りがするものを買ったり、文化的な活動を支援することをクールとする風潮も手伝って、日本人を含めたお金持ちたちが積極的に現代アートを蒐集し、作品を買うことがトレンドになっているんです。
── ここ数年、実業家の前澤友作さんがバスキアの作品などを高値で購入し続けていることが話題になっています。
三潴 彼はその典型ですよね。もともとストリート・カルチャーのバックグラウンドをもっている方らしく、ビジネスで成功した時に、バスキアのようなグラフィティ・アートにシンパシーを感じたってことなんでしょう。でもバスキアの作品を買うことによって、彼の名前が世界中であっという間に認知された。フェラーリを買っても絶対にそうはならないけれど、100億円を超えるバスキアを買ったらニュースになって、彼自身のブランディングになるわけですよ。

三潴 日本を代表するコレクターとしては、高橋龍太郎さんという精神科の医者がいます。1990年代の初めから日本のアート、特に若い作家たちを幾つかのギャラリーから定期的に購入していた人です。草間彌生や奈良美智、村上隆、会田誠あたりも買ってました。30年前の草間さんの作品は、まだとても安かったし、おそらく数十万円の単位で買っていたものが、今では10億、20億円となり、膨大な価値をもつコレクションになっています。

高橋龍太郎さん。写真/Elena Tyutina
大田区立龍子記念館にて「川端龍子vs.高橋龍太郎コレクション ―会田誠・鴻池朋子・天明屋尚・山口晃―」が開催中。
それから岡山のクロスカンパニーという会社の石川康晴さんは、色々話題に事欠かない人でもありますが、地元で芸術祭を最近始めたりして市場の活性化に貢献しているし、機械加工製品メーカーのミスミグループの田口弘さんは“タグチアートコレクション”で有名。初めはアメリカのポップアートや版画にフォーカスしていましたが、その後日本の現代アートも幅広く集めるようになったようです。若手では川崎祐一さんが良いコレクターになってきましたね。
三潴 そうですね。なかでも桁違いなのが、ベネッセホールディングス名誉顧問の福武總一郎さん。瀬戸内海の直島や豊島に作った美術館や、瀬戸内トリエンナーレでの活動でも知られています。福武さんは作品を購入したらそのための建物を建てて、コレクションしたものを必ず公開するという非常に前向きな人です。そうしてできたミュージアムは今や日本を代表する観光地になっているし、世界のアート史にも名を刻む素晴らしい蒐集家だと思っています。
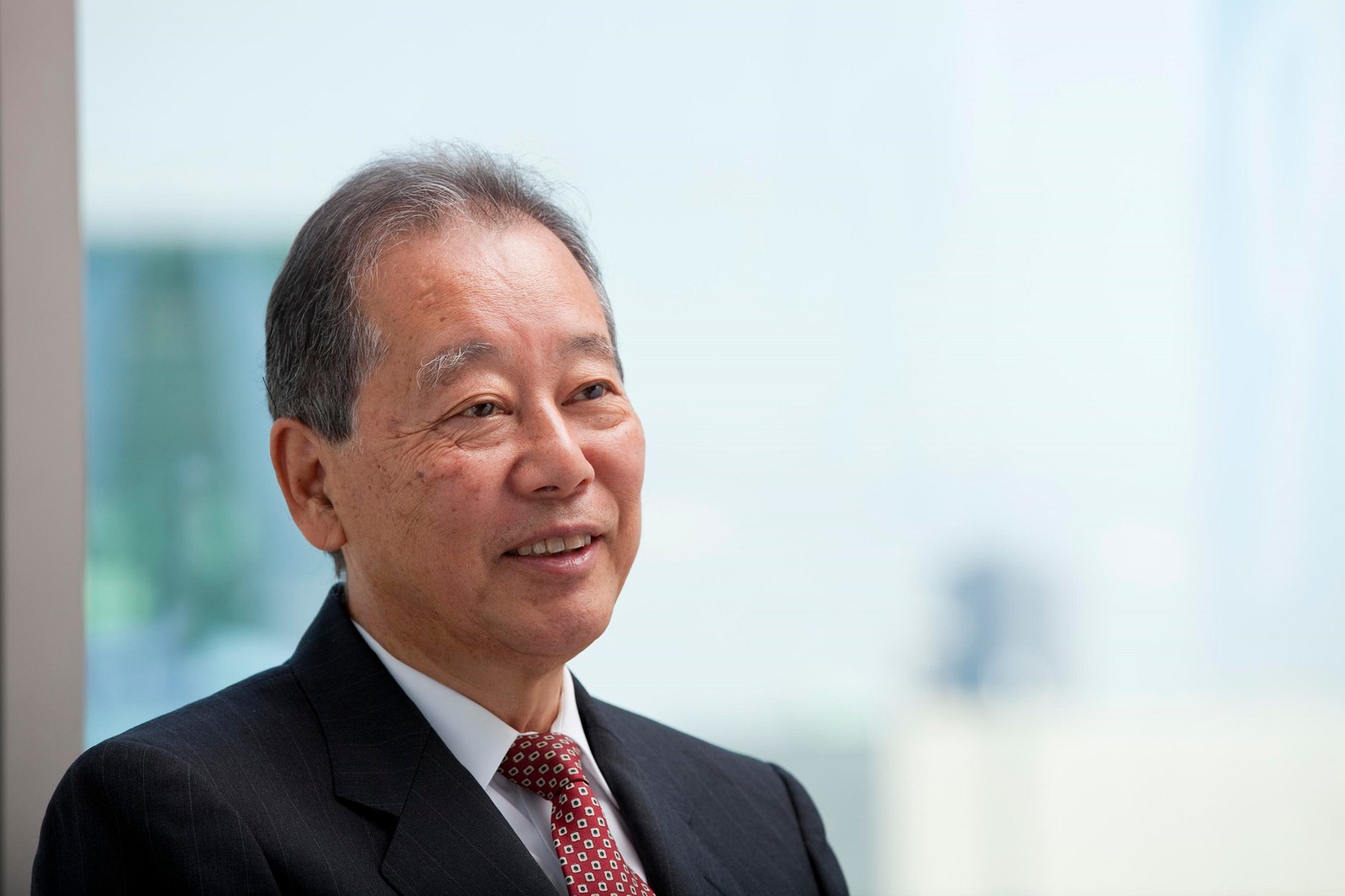
ちなみにアメリカの『アートニュース』誌が発表する「世界のトップコレクター・トップ200」にも掲載されているファーストリテイリングの柳井正さんは、実は現代アートについてはあまり寄与していない印象ですね。柳井さんとか、ソフトバンクの孫正義さんあたりがもうちょっとお金を投入してくれれば、国内のマーケットが活性化するのではないかと期待していますけど。
インスタや通販サイトで低予算から初めてみるのも手
三潴 あまり具体的な名前をあげられない事情があるのですが、独自の路線という点でいうと米谷健+ジュリアかな。この夫妻は京都の吉富というところで、無農薬で米や野菜を栽培し、本格的に農業をやりながらアート活動をしている。以前はオーストラリアに住んでいたから、豪州代表でヴェネチア・ビエンナーレに参加したりしている、国際的な作家です。
▲ 米谷健+ジュリアの作品から。《Dysbiotica》展示風景、2020 撮影/宮島径 ©︎Ken+ Julia Yonetani, Courtesy of Mizuma Art Gallery
▲ 《Dysbiotica》展示風景、2020 撮影/宮島径 ©︎Ken+ Julia Yonetani, Courtesy of Mizuma Art Gallery
▲ 米谷健+ジュリア 撮影/Josh Robenstone

▲ 米谷健+ジュリアの作品から。《Dysbiotica》展示風景、2020 撮影/宮島径 ©︎Ken+ Julia Yonetani, Courtesy of Mizuma Art Gallery

▲ 《Dysbiotica》展示風景、2020 撮影/宮島径 ©︎Ken+ Julia Yonetani, Courtesy of Mizuma Art Gallery



▲ 米谷健+ジュリア 撮影/Josh Robenstone
三潴 KYNE(キネ)とかBackside works.(バックサイド ワークス)とか、1980年代・90年代のカルチャーにインスパイアされた若い世代のアーティストが、マーケットを賑わせ始めています。彼らの作品はすでに国外でも幅広く支持され始めていて、その理由の一つはシティポップという音楽の世界と結びついている点です。その背景には、竹内まりやや山下達郎といった日本の80年代のポップソングがカッコいいというトレンドがあって、藤原ヒロシがKYNEとコラボしたミュージックビデオなんか、最高にクールに見えるようです。でも商業主義に走り過ぎているのは懸念材料だし、漫画家の江口寿史のテイストを彷彿とさせるのも気になります。
三潴 国内外を問わず、昨今の現代アート作品には見たことのある既視感が漂っていますね。これは世代単位で自己模倣を繰り返しているせいかもしれません。安易に流行が蔓延する時代のアートは危ういですよ。
── なるほど。KYNEやBackside works.に対するアート業界の反応はどうなんですか?
三潴 日本の “アカデミックな層” は否定的ですね。大人の塗り絵だとか、賞味期限2年とか言っちゃって。実を言うと僕も最初はそう思ったのだけど、考えてみたら30年前に奈良美智、村上隆、会田誠が出てきた頃にも、彼らの世代の作家の作品について「こんなのアートじゃない、アニメだ、漫画だ!」ってまったく同じことを言われていたんですよ。どうもアカデミックな人たちはコンセプチュアルアートに対するこうした固定概念が強くて、それに洗脳されている感じもする。
僕からしたら、大人の塗り絵的な感じでありながら、それがアートになっていて、これを支持する層が海外、しかも主にアジアにいるっていう構図はとても興味深いのですが。これからのアーティストは日本という国の中だけに限定して活動するのではなく、インスタ等のインターネットを通じた世界が一つのアクチュアリティがあって、新しいアートが生まれる可能性はそこにあるんじゃないかなと思っています。
三潴 作家自身も含め、こういう新しいアートに関わる層はミレニアム世代がメインだから、売買の場はオンラインが主流となっています。子どもの頃からインターネットに親しんできた層だから、アート作品もネットで買うんです。ちなみに今、こういった作品が一番売れる場所は実はギャラリーではなくて、インスタなんですよ。若い作家でもインスタで売れるから、みんなそこで発信している。あと現代アートのオンライン販売に特化したtagboat(タグボート)というサイトがあって、デビュー戦はそこで、っていう作家も多い。そういうところで駆け出しのアーティストの作品を狙うなら、5万、10万円くらいで買えるからオススメです。で、そこそこ実績を上げた作家は、その後ギャラリーに所属するようになるから、ギャラリー巡りも重要ですね。
オークションは事前に見積もりを立て、余裕を持った予算感でのぞむべし
三潴 全然大丈夫ですよ。カタログもタダでもらえるし、オンラインでも参加できるし。サザビーズ、クリスティーズなどの大手オークションだと事前にクレジットカードを登録したり、信用照会もかけられたりしますけど。
── でも、ある程度の予算がないと難しいですよね?
三潴 というか、オークションは基本的にはまず予算を決めることから始めるべきです。予算を決めないで熱くなって手挙げていたら、高いものを買ってしまって後で支払いに苦労しますから。支払いが滞るとペナルティもつくし、利息も高いので、そこは慎重にやらなきゃいけない。一般的に、購入後2週間以内には支払いを済ませなければいけません。
三潴 通常オンラインに出品予定作品のエスティメート(見積もり)が掲載されているから、お目当ての作品をチェックして、あらかじめ計算しておく。例えばそこに100万から150万円と書いてあったら、実際に買える値段は高い方の金額の150%から200%くらいが相場となることが多いから、その場合は225万から300万円ぐらいの間を想定しておくんです。
あと、例え225万円で落札できたとしても、そこから手数料を25%ほど取られるので、最終的には300万円くらいになる予算感でのぞむのがいい。手数料は買い手、売り手の双方にかかってきます。日本のオークションハウスの買い手の手数料は平均10%から15%ですが、サザビーズやクリスティーズといった大手だと27.5%、場合によっては30%なんてことも。特に買いの手数料は高いです。
三潴 今、旬な作品が買えるのはSBIアートオークションですね。2か月に1回オンライン、3か月に1回代官山の会場で開催されています。前述のKYNEやBackside works.の作品も取引されていて、ちょっと前までは数十万円だったんですが、今や3000万くらいの値がつくことも。それ以外だとシンワアートオークションや毎日オークション、エストウエストオークションあたりもチェックしておくといいかもしれません。
── 税金についても気になります。そのあたりについて教えていただけますか?
三潴 年収にもよるのですが、世界的にみると日本の税金はけっこう高いです。売る方に関していうと短期譲渡と長期譲渡があって、短期は5年以内で売ると買ったコストを引いた額に対して税金がかかり、所得によってはその税率が5割になることも。100万円で買ったものを200万円で売ったら利益的には100万円ですが、その半分の50万円は税金でもっていかれるということですね。それが例えばシンガポールだったら、いわゆるキャピタルゲインに関する税金は免除されるので、アート作品の売買で利益が出ても税金が発生しない。
三潴 5年以上所有すると長期とみなされます。同じ100万円の利益をあげても、そこから50万円を差し引けます。さらに残った50万円の半分、25万円に対してだけ税金がかかる仕組みです。だから作品を買うなら、5年以上の長期譲渡をマストに考えていた方がいい。まあ、その間に価値が下がっちゃうなんてこともあるのですけど。税率については税理士に相談してみてください。
── そのへんは市場の動向を見ながらですね。他に注意するべき点はありますか?
三潴 海外で作品を買って日本に持ち帰ると、消費税が10%課税されるし、相続の際にも税金がかかります。ちなみに香港ではアートの輸出入に関してはタックスフリー、フランスでは文化的なものに対する相続税は軽減される。日本にはそういう概念が根付いていなのだけれど、文化を残すという観点から考えると、変えていくべきだと思っています。例えばそれが美術館に展示されるレベルの作品の場合、相続税を免除するくらいのことをね。今、文化庁は制度改革に向けて動いているようなので、今後に期待したいですね。

●三潴 末雄(みづま・すえお)
ミヅマアートギャラリー エグゼクティブ・ディレクター。東京生まれ。成城大学文芸学部卒業。1980年代からギャラリー活動を開始、1994年ミヅマアートギャラリーを東京・青山に開廊(現在は新宿区市谷田町)。2000年から海外のアートフェアに積極的に参加。2008年に北京にMizuma & One Galleryを、2012年にシンガポールにMizuma Galleryを、2018年にニューヨークにMizuma & Kipsを開廊。著書に『アートにとって価値とは何か』(幻冬舎刊)、『MIZUMA 手の国の鬼才たち』(求龍堂刊)。
ポートレート撮影/野口博
















