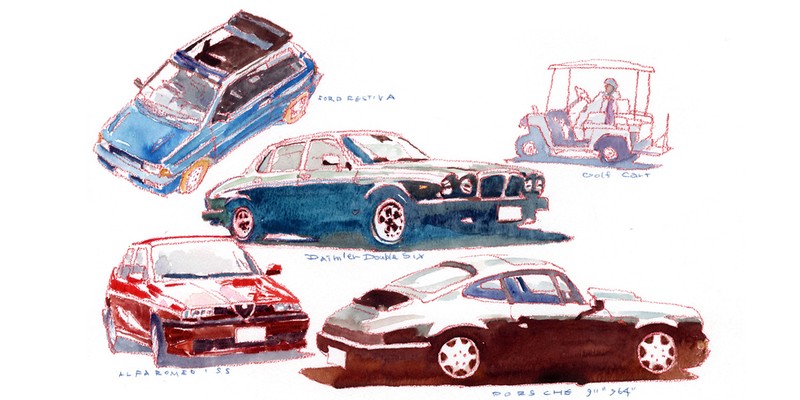2024.01.26
東京に憧れない変わり者シェフ二人が地方の食文化を大化けさせるキーパーソン⁉
美術館に飾るような器で佐賀の美食を楽しむプレミアムレストラン「USEUM SAGA(ユージアム サガ)」に伺ってきました。5回目となったこのイベントの現在地とは? 成果と課題とは?
- CREDIT :
文/森本 泉(LEON.JP)

新しいローカルガストロノミーのあり方を提唱する「USEUM SAGA(ユージアム サガ)」
コロナ禍による4年ほどの自粛期間があったとはいえ、近年、訪日外国人旅行者数は増え続け、彼らの多くが「日本食」を求めてやってくることから、その目的を叶える観光推進策のひとつとして「ガストロノミーツーリズム」という言葉があちこちで聞かれるようになってきています。
観光誘致に繋がるのはもちろん、それをきっかけに地元の産業が発展すれば良いことづくめ。既に国内でも多くの自治体で様々な取り組みが行われており、「USEUM SAGA」もそんなイベントのひとつと捉えられます。

今回のイベントでは、佐賀市内で「カレーのアキンボ」というスパイス料理の人気店を開く川岸真人シェフと、沖縄・宮古島を拠点に琉球ガストロノミーを提唱して高い評価を得ている渡真利泰洋シェフがコラボレーションして、佐賀食材の新たな魅力を伝える特別なディナーを振る舞いました。
ふたりの地元愛、料理愛が矢のように飛び交う刺激的なディナーの中身は写真でお伝えするとして、本記事ではイベントの仕掛人である佐賀県流通・貿易課の安冨喬博さん、そして参加した二人のシェフにも話を伺いました。5回目となったこのイベントの現在地とは? 成果と課題とは?

県外から人を呼べるレストランができれば万事OKではない
安冨喬博さん(以下、安冨) そこに関してはどちらかと言うと二次的な、副産物的なこととしてはあるのですが、まずは佐賀の料理人さんたちにスポットライトを当てながら、彼らの可能性を発信していこうというのが現在の思いです。
それこそ、ここ数年でローカルガストロノミーがわりと急速に全国的に広がって、いろんな媒体で注目の地方のレストランみたいな取り上げ方もされています。ただ、旅の目的になるレストランとか、わざわざ県外の人が食べに来るレストランは、ちょっと角度を変えると地元の人が足を運ばないというか。言ったら県外のお客様100%で、地元の人は、「あ~あそこはね」みたいな。
それでいいのかなという思いがあります。私はそういうお店ではない、地元の人にも愛されるし、でも外の人からも人気があるような。地元の人が「あなた、佐賀に来たんだったら、あそこ行ってみなよ」という、そういうお店が増えて欲しいと思っているのです。

安冨 食の在り方は今とても多様化しています。その中で、ローカルガストロノミーが注目されていて、実際にそういった取り組みをされている地域のシェフとコラボしたいという思いは「USEUM SAGA」の当初よりありました。前回の「とおの屋 要」(岩手県)さんのように、地域で活躍するシェフから学べるところも多いと思いますし、佐賀県のシェフや産地がどんな風に見えているのかも1つ勉強になるかなと思っています。
さらにローカル×ローカルというコラボはお客様の反応も大変良く、県として手ごたえを感じていたので今回もこの形にさせていただきました。
実は、このプロジェクトを始める前は、3つ星とかアジアベストレストランなどのランキングシェフとか、そういう方々を佐賀にお呼びして、食材や器を有名なシェフの方たちに使ってもらうことでプレゼンスを上げるということもやっていました。
でも、コロナ禍というのもあって、なかなか外からシェフたちを呼べない状況となり、私自身も地元の料理人さんたちは、普段、地元の食材や器とどう向き合っているんだろうという素朴な疑問があったので、地元でヒアリングをしてきました。
▲ この日のディナーはデザートまで入れると全12皿。どれもが独創的かつ味わい深い印象的なメニューでしたが、そのすべてをご紹介。1皿目は「水イカのパフェ」。イカ・菊芋・パパイヤを組み合わせた色鮮やかな一品。器は江戸時代から一子相伝で「鍋島焼」を継承してきた今右衛門窯。
▲ 2皿目は「カキトカブ」。東鶴酒造の酒粕、乾燥させた月桃を使ったアイスクリームの上に大ぶりの生ガキ。上にはカブとカブのジュレがかけてある。器は焼き物を窯に入れて焼成する際、焼き物が付着してしまわないよう焼台として下に敷く窯道具の「ハマ」を使用。
▲ 3皿目は「ポーポー」。ポーポーは沖縄のクレープのような料理。中身は伊良部島のなまり節をカレーにしたものと、生のヨモギ。料理の下に敷いているのは梶の木の繊維を粗く繋いだ和紙のプレート。製作した名尾手すき和紙は梶の木の栽培から製品まですべての工程を一貫して行っている。

▲ この日のディナーはデザートまで入れると全12皿。どれもが独創的かつ味わい深い印象的なメニューでしたが、そのすべてをご紹介。1皿目は「水イカのパフェ」。イカ・菊芋・パパイヤを組み合わせた色鮮やかな一品。器は江戸時代から一子相伝で「鍋島焼」を継承してきた今右衛門窯。

▲ 2皿目は「カキトカブ」。東鶴酒造の酒粕、乾燥させた月桃を使ったアイスクリームの上に大ぶりの生ガキ。上にはカブとカブのジュレがかけてある。器は焼き物を窯に入れて焼成する際、焼き物が付着してしまわないよう焼台として下に敷く窯道具の「ハマ」を使用。

▲ 3皿目は「ポーポー」。ポーポーは沖縄のクレープのような料理。中身は伊良部島のなまり節をカレーにしたものと、生のヨモギ。料理の下に敷いているのは梶の木の繊維を粗く繋いだ和紙のプレート。製作した名尾手すき和紙は梶の木の栽培から製品まですべての工程を一貫して行っている。
器に関してはもっと厳しくて、そもそも佐賀の飲食店さんであっても有田焼を使っていないとか、有田に行ったことがないとか。もちろん、中にはすごく地元にこだわっている料理人さんたちもいるのですが、そういう方ばかりではない。そこをどうにかするためにも、僕らは地元の料理人さんにもう少し目を向けるべきだと思ったのです。
蓄積した情報やネットワークのノウハウを地元に還元できていなかった
安冨 はい。県の事業としてのミッションは地元の農家さんとか焼き物屋さんと、地元のレストランさんをマッチングすることで、そこで取引が生まれていく。産業としてちゃんと地元でお金が回っていく仕組みを作っていこうという、そういう事業成果と言うか事業目的を掲げながらやっていくということもあります。

でも、僕らは外の料理人さんたちにしか目を向けていなかったし、蓄積したノウハウを地元に還元できていなかった。地元で佐賀の食材で勝負してくれる料理人さんたちを、ちゃんとサポートしていくという、そこの意識が少なかったなと反省しています。
安冨 佐賀の食材と器をベースに、地元の料理人さんたちと組み合わせて、それをイベントごととしてしっかり発信をしていく。そうすれば地元の料理人さんたちの食材とか器への理解も深まっていくし、その中から今日の川岸シェフみたいに、しっかり評価をいただける方が出てくると、どんどん注目も集まって、佐賀にもローカルガストロノミーのお店が増えていくんじゃないかなと思っています。
▲ 4皿目は「カニと豆腐ようのスープ」。もともとは、渡真利シェフのスペシャリテで蟹と泡盛を豆腐ように漬け込んで生で食べる「スンビュウガニ」を出す予定だったが、用意した渡り蟹が生食に適していなかったこともあり、急遽カレースープに変更。器は文祥窯のワイングラス風カップ。
▲ 5皿目は「がめ煮 ドゥルワカシー」。肉はすっぽんを使用。ドゥルワカシーは田芋をペースト状にした沖縄の伝統料理。上にのった緑色のものは長命草。日本を代表する青磁作家で人間国宝に認定された中島宏(弓野窯)氏の作品。
▲ 6皿目は「ジューシー」。ジューシーは炊き込みご飯のこと。生海苔・魚の出汁で煮込まれたご飯に、しっかりと酸味のあるキュウリのスライス、海から収穫した海苔をそのままの状態で乾燥・焙煎することで海苔本来の香りと味わいが楽しめる香味干しがのっている。器は柿右衛門窯の飯碗。江戸時代に日本で初めて色絵磁器を完成させた窯。

▲ 4皿目は「カニと豆腐ようのスープ」。もともとは、渡真利シェフのスペシャリテで蟹と泡盛を豆腐ように漬け込んで生で食べる「スンビュウガニ」を出す予定だったが、用意した渡り蟹が生食に適していなかったこともあり、急遽カレースープに変更。器は文祥窯のワイングラス風カップ。

▲ 5皿目は「がめ煮 ドゥルワカシー」。肉はすっぽんを使用。ドゥルワカシーは田芋をペースト状にした沖縄の伝統料理。上にのった緑色のものは長命草。日本を代表する青磁作家で人間国宝に認定された中島宏(弓野窯)氏の作品。

▲ 6皿目は「ジューシー」。ジューシーは炊き込みご飯のこと。生海苔・魚の出汁で煮込まれたご飯に、しっかりと酸味のあるキュウリのスライス、海から収穫した海苔をそのままの状態で乾燥・焙煎することで海苔本来の香りと味わいが楽しめる香味干しがのっている。器は柿右衛門窯の飯碗。江戸時代に日本で初めて色絵磁器を完成させた窯。
── そういうお店が増えていくことで、結果として、観光客の増加にも繋がっていけばよいと。
安冨 そういうことです。
外からの評価があることで地元も誇りが持てるようになる
安冨 やはり地元の方たちの佐賀に対する評価というのが、まだまだ低いのかなと。知事が「佐賀さいこう」というフレーズを仰って、地元を愛する評価が上がってきているのは確かなのですが、まだまだ足りていない。だから、福岡とか、外に足が向いてしまうというのがあるのかなと。
やはり対外的な評価というのは大事で、それがないと地元も誇りが持ちづらいというのはあると思うのです。なので、こういうイベントで外の方にも食べていただいて評価をしてもらうという要素も作らないといけないかなと、意識的にメディアの方にも来ていただいて、発信を続けているということです。

安冨 実際、このイベント自体、最近は結構、地元のお客さんが多いのです。僕らも最初は2万円とか3万円という価格なので、お金に余裕があって普段からそういうレストランを食べ歩いているような、一部の方々に、お客さんが固定化するんじゃないかなと思っていたのですが違った。結構新規の、しかも地元のお客さんが多くて。佐賀の中にもちゃんと価値をわかっていただいて、そこに対価を払っていただける、そういうお客さんがいるんだなと。しかもそういった方たちが回を重ねるごとに増えて行っている。だから裾野を広げて行っているという、自分の中での手ごたえはあります。
安冨 そうやって食べ手側の意識を変えていくというのも僕らのテーマかなと。お客さんが増えていけば、お店も営業的に助かるわけだし。そうすれば料理人の方も、もっと自分も新しい料理で勝負しようかなとか、思えるじゃないですか。そういう意味では少しずつですけど、裾野が広がって行ってるなと思います。
あとは、メディアの方にもしっかり発信していただいているので、結構、他の自治体さんや食業界の方々からも、佐賀って面白いことやってるよね、こんなことを行政レベルでやってる地域はないよとか、そういうお声をいただいたり。佐賀の地域性みたいなものを磨いていくというこのプロジェクトが、他の地域の方々にも参考にしていただけるような、そういう評価をしていただいている部分もあるのかなと感じます。
▲ 7皿目は「イラブチャー」。イラブチャーはナンヨウブダイのこと。自家製タイカレーソースにイラブチャーを漬け込み、銀杏と共に月桃で、沖縄の葉っぱ・月桃で包み蒸しにした。器は人間国宝に認定された井上萬二氏の作品。
▲ 8皿目は「祝いの山羊 ケバブ」。スパイスで味付けした山羊の挽肉を焼いている。仕上げに藁とシナモンの根っこの薫香を纏わせてた。器は柿右衛門窯。
▲ 9皿目は「祝いの山羊 山羊そば」。山羊の出汁を使ったスープ、やや太めの麺。ヨモギをお椀の底に隠すのが宮古島式だそう。器は中里太郎衛門陶房。

▲ 7皿目は「イラブチャー」。イラブチャーはナンヨウブダイのこと。自家製タイカレーソースにイラブチャーを漬け込み、銀杏と共に月桃で、沖縄の葉っぱ・月桃で包み蒸しにした。器は人間国宝に認定された井上萬二氏の作品。

▲ 8皿目は「祝いの山羊 ケバブ」。スパイスで味付けした山羊の挽肉を焼いている。仕上げに藁とシナモンの根っこの薫香を纏わせてた。器は柿右衛門窯。

▲ 9皿目は「祝いの山羊 山羊そば」。山羊の出汁を使ったスープ、やや太めの麺。ヨモギをお椀の底に隠すのが宮古島式だそう。器は中里太郎衛門陶房。
地方では若い料理人さんたちがなかなか育たない
安冨 課題は本当にいろいろあって。でも、まずは若い料理人さんたちがなかなか育たないということでしょうか。東京なら20代、30代前半ぐらいの若いシェフの新しいレストランができたとか、注目の若手シェフがいるよみたいな話はいくらでもあるのでしょうが、どうしても佐賀だとそうはいかない。
これは、佐賀だけの問題ではないと思いますが、地方でお店をやるとなると、お客さんの数も限られるし、払えるお金の上限とかも東京と比べると、大分下げなければいけない。だから、どうしてもお店自体も自分一人で完結できるような規模感のお店になりがちです。ワンオペとかで、カウンター6席、8席ぐらいとか。それはそれで料理人さんの選択肢としては全然アリだと思うのですが、逆にそういうお店ばかりになると、若い子が働ける環境が少なくなってしまう。だから外に出て行ってしまうという。

安冨 それをレストランレベルでやれるかというのはなかなか難しいところがあります。地方でレストランをやってみたいというシェフがいた時に、あくまでソフトレベルでいろいろ仲介をするなどのサポートはできると思うのですが、それ以上は難しい。
例えば全然アイデアレベルですけれど、誰でも使えるようなラボキッチンみたいな箱があって、2週間とか3週間とか、ショートステイみたいな感じで、佐賀に滞在していただく。そこでいろいろ佐賀の人たちと交流をしながら食材を勉強してみたり、焼き物の産地について学んでみたりとか。で、そこのラボキッチンで料理を作ってみる。そういうものを拠点としてどこかしらに作れると、もう少しいろんな人たちが交流できるポイントが作れるのかなと何となく考えたりはしてるのですが。
いずれにしろ、僕ら行政だけでやるのは限界があります。だから地元の企業とか、民間の方々の力もお借りして、佐賀に若い料理人さんたちが、学びに来られるような、そういう環境とか場所を一緒に作っていきましょうみたいな。ある種、民間の人たちの力がないと継続するというのは難しいなと。そこも含めて僕らの課題かなと思っています。
▲ 10皿目は「祝いの山羊 山羊カレー」。山羊肉の煮込みカレー。サフランやミント、カシューナッツと一緒に炊いたバスマティライス。泡盛の酒粕(宮の華酒造)を煮詰めた黒いソースを添えて。器は李荘窯業所。
▲ 11皿目はデザートの「アイス」。宮古島の山羊ミルクと山羊チーズ、1年熟成の豆腐ようにシナモン、ナカシマファームのブラウンチーズにカスリメティ。3種類のアイス。器は人間国宝に認定された井上萬二氏の作品。
▲ 12皿目はデザートの「オリオンビール」。グラスの中身は、オリオンビールを使ったアイスクリーム・海葡萄・蜜柑・ポン菓子などを使ったパフェのような組み合わせ。グラスを支える土台は宮古島の浜辺の砂。器は江戸時代末期に創業した徳幸窯。業務用食器でも評価が高い。

▲ 10皿目は「祝いの山羊 山羊カレー」。山羊肉の煮込みカレー。サフランやミント、カシューナッツと一緒に炊いたバスマティライス。泡盛の酒粕(宮の華酒造)を煮詰めた黒いソースを添えて。器は李荘窯業所。

▲ 11皿目はデザートの「アイス」。宮古島の山羊ミルクと山羊チーズ、1年熟成の豆腐ようにシナモン、ナカシマファームのブラウンチーズにカスリメティ。3種類のアイス。器は人間国宝に認定された井上萬二氏の作品。

▲ 12皿目はデザートの「オリオンビール」。グラスの中身は、オリオンビールを使ったアイスクリーム・海葡萄・蜜柑・ポン菓子などを使ったパフェのような組み合わせ。グラスを支える土台は宮古島の浜辺の砂。器は江戸時代末期に創業した徳幸窯。業務用食器でも評価が高い。
東京でお店を開いたって何も面白いと思えなかった
それでも、若い料理人に地元に目を向けてもらうのは容易なことではないでしょう。そんななか、イベントのシェフを務めた川岸真人シェフと渡真利泰洋シェフはどちらも地元にとどまって活躍しています。ともにまだ39歳(イベント開催時)と若いふたりですが、彼らは何故、東京ではなく地元を選んだのでしょう? その思いを聞いてみました。
まずは沖縄・宮古島出身の渡真利泰洋シェフ。20歳で上京し、世界で修業を積んで8年前に31歳で沖縄に戻りました。

● 渡真利泰洋(とまり・やすひろ)
1984年沖縄県宮古島市生まれ。20歳で上京、イタリア料理を学ぶ。その後、数店のフレンチで修業を重ね、渡仏。「Joel Robuchon」を始めとしたパリの名店にて研鑽を積み、帰国後31歳で伊良部島にある「Restaurant Etat d'esprit」総料理長に就任。世界の人々のための、日本のレストラン「The Japan Times Destination Restaurants 2021」の10組に選出。フランスのグルメ雑誌「ゴ・エ・ミヨ2022]で沖縄最高得点の15.5点獲得。2019年には次世代を担う実力シェフとして全国15人のひとりに選出。ただ今、独立開業準備中。
渡真利泰洋シェフ(以下、渡真利) 僕の場合は天然ですよ。天然なので東京で何をやっていいかわからなかった(笑)。東京でクリエイティブとかオリジナリティって言ったって何やるんだろう? 東京でフランス料理やるの? 単純に面白くなかったというか。ワクワクしなかったというか。やっても続かなかったんじゃないかな。
── 沖縄の食材が身近にないとかそういうことですか? ワクワクしないのは。
渡真利 面白いと思わなかったんですね。僕が東京でお店を開いたら、東京の食材も使うかもしれないじゃないですか。誰でも使うようなフォアグラとか使うかもしれない。でも、誰でもやるようなことを僕がやって何が面白いんだろうなって。

渡真利 まぁそうですね。
── 自分が自分らしい料理を作るんだったら地元が一番という?
渡真利 それがお客さんも一番面白いんじゃないかと。僕もずっと、いわゆる地方でやっている地元の食材を使ったフランス料理をやっていたんですけど、あるグルメイベントをきっかけにガガン(※)という料理人との出会いがあって。彼はストリートフードだ、B級だと言われたインド料理をファインレストランの料理に押し上げた人です。僕は「これだな! 沖縄でもできる!」と思ったんです。
食の不毛の地と呼ばれているのかわからないですけど、美味しいものないよねと言われてる沖縄だけど、でも実は歴史を振り返っていくと、美味しいと言われるものはあったんですよ、かつて。それ、面白くないですか?
今はもうフレンチという事を意識しなくなりました。100年後も残る、新しい沖縄料理というものを作っていきたいんです。
なんで自分は東京にいるのだろうという違和感を感じていた

● 川岸真人(かわぎし・まこと)
1984年佐賀県佐賀市生まれ。佐賀県立佐賀北高校普通科芸術コース卒業。日本大学芸術学部美術学科卒業。都内の寿司屋で3年修業を積み、2010年、東京・錦糸町に「カレーのアキンボ」をオープン。2015年、佐賀に戻り、完全予約制・コースのみのスタイルにリニューアル。週に一度は生産者を訪ね、その時々で出会った食材をベースに料理を組み立てる。「ミシュランガイド2019福岡・佐賀・長崎版」ビブグルマン獲得。「ゴ・エ・ミヨ2023」では佐賀県内7店舗の1店に選ばれる。
川岸 僕、東京でやっていたのが錦糸町って、墨田区だったんですけど。墨田区ってずっと東京に住んでいる人が多い街なんですよ。小学校から中学校からみんな友達みたいな。そういう中にいて、自分は地元から離れてそこにお店をやっていて、なんで自分はここにいるのかなとか感じて。東京というのは若干ファンタジー感、地に足がついてないって言ったら変なんですけど、なんか、根本がない人たちがいっぱいいて、自分もその一人だなと。
でも、錦糸町に住んでいる人たちは本当に地元の祭りを愛していて、なんだったら、佐賀の人とかに似てるんですよ。で、やっぱり僕は最終的に佐賀とか地元に帰ってこなきゃいけないんだろうなというのは、その墨田区の人たちを見て思ったんです。

川岸 はい。お店を始めて5年以内には地元に帰ろうっていうのはあって、で帰ってきた。でもそうしたら、佐賀の食材が凄い美味いってことに気づいて。東京でやっていた時はラムのキーマカレーというのがスペシャリテだったんですけど、もうそれもやめて。佐賀の食材だけでいこうと決めて、どんどん地元の生産者さんたちと繋がっていくと、もう、皆さん、本当にプライドをもってやっている。
その人たちから託されて、これ絶対生かしてあげたいって思うと、自分の料理がどんどん佐賀の食材に限定されていって、そこでなんか、ルールを作ることで自分のオリジナリティが逆に出来てきたなって思うんです。
そうすると、僕、毎週畑に行くんで、これを強いスパイスで殺しちゃうのは自分にはもうできないと思って、だんだん引き算の料理になっていった。そこでなんか、佐賀に帰って来ることで、自分の料理が出来上がっていったというのは、ありますね。

人を惹きつける変わり者のパワーが地方の拠点となる?
でも、逆に時代を動かすのは彼らのような情熱を持った変人なのだろうなと素直に思いました。彼らを慕い、彼らに憧れる若者は絶対に出てきます(すでに出ているのかもしれません)。その若者たちが同じように故郷に戻って苦労しながらも独立していく。理想の連鎖が起きるとすれば、結局それは人の力によるしかないのでしょう。
だとすれば、食のイベントで渡真利シェフがガガン氏に会って人生が変わったように、若い料理人にこそ、この二人のような才能ある素晴らしいシェフと出会える機会が増えればよいなと思いました。県ではすでに先述のようなセミナー(サガマリアージュセミナー)なども開催していますが、安冨さんが言っていたラボキッチンもぜひ実現してほしいものです。